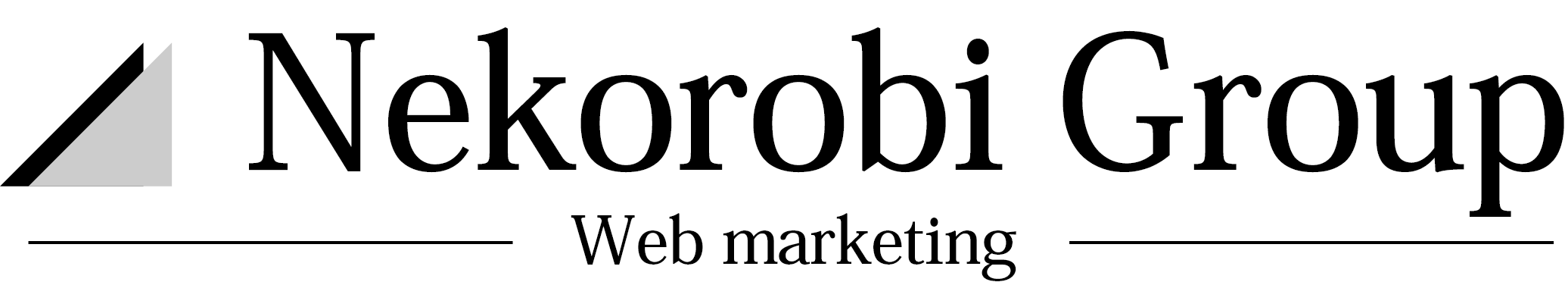「うちの会社も何か話題になるような発表ができないだろうか…」そんな風に考えたことはありませんか?中小企業の社長にとって、大手企業のように注目を集めるプレスリリースを出すのは簡単なことではありません。しかし、「調査リリース」という手法を使えば、会社の規模に関係なく、メディアに取り上げられる可能性の高い情報発信ができるのです。
調査リリースは、通常の商品発表やサービス告知とは全く違ったアプローチで企業の認知度を高める方法です。特に重要なのがデザインの力。同じ調査データでも、見せ方次第で読み手の印象は大きく変わります。今回は、広報のプロに依頼する前に知っておきたい調査リリースの基本と、デザインで差をつけるポイントを詳しく解説していきます。
調査リリースとは?普通のプレスリリースとの3つの違い

調査リリースの基本的な定義
調査リリースとは、企業が独自に実施したアンケートや調査の結果をまとめ、プレスリリースとして発表するPR手法のことです。例えば、化粧品会社が「働く女性の美容意識調査」を実施し、「8割の女性が『時短メイク』を重視」という結果を発表したり、IT企業が「中小企業のDX導入実態調査」を行い、「7割の企業がテレワーク導入を検討中」といった情報を世の中に発信します。
この手法の特徴は、商品を直接宣伝するのではなく、業界の実態や消費者の本音を客観的なデータとして提示することです。そのため、読み手にとって有益な情報として受け入れられやすく、結果的に企業の信頼性向上につながります。
違い①:直接的な宣伝ではない
通常のプレスリリースとの最も大きな違いは、直接的な宣伝ではないという点です。新商品の発売告知であれば「新発売!今すぐお買い求めください」というメッセージが前面に出ますが、調査リリースは「こんな興味深いデータがありました。皆さんはどう思われますか?」という客観的な情報提供の形を取ります。
この違いにより、メディア関係者からの警戒心が薄れ、「読者に有益な情報」として記事化される可能性が高まります。実際に、広告色の強いプレスリリースは敬遠されがちですが、調査リリースは「ニュース価値のある情報」として扱われることが多いのです。また、SNSでシェアされる際も「面白いデータを見つけた」という形で自然に拡散されやすいという特徴があります。
違い②:話題性の作りやすさ
二つ目の違いは話題性の作りやすさです。調査リリースでは「85%の管理職が『部下のやる気低下』を実感」「意外!7割の夫婦が『家事分担に不満なし』」といった形で、読み手の予想を裏切る結果や、社会の関心事に関するデータを提示できます。
特に効果的なのは、世の中のトレンドや季節感と絡めた調査です。例えば、働き方改革が話題の時期に「リモートワーク実態調査」を発表したり、夏のボーナス時期に「家計の使い道調査」を実施したりすることで、メディアの注目を集めやすくなります。また、「前年比○○%増加」「過去最高の数値」といった時系列比較を盛り込むことで、ニュース性をさらに高めることができます。
違い③:継続的な効果が期待できる
三つ目の違いは継続的な効果が期待できることです。新商品発表のプレスリリースは発売日を過ぎれば古いニュースになりますが、調査データは「業界の動向を示す資料」として長期間活用できます。
営業現場では「業界全体の○○%が課題に感じている問題を、弊社のサービスで解決できます」といった形でクロージング資料として使用できます。ウェブサイトに掲載すれば、検索エンジンからの流入も期待できます。さらに、同じテーマで年次調査を継続することで「○○白書」として権威性を高め、業界のオピニオンリーダーとしてのポジションを確立することも可能です。実際に、毎年発表される「働き方調査」や「消費者動向調査」などは、その企業の代名詞として認知されています。
調査リリースのデザインで失敗する3つのパターン
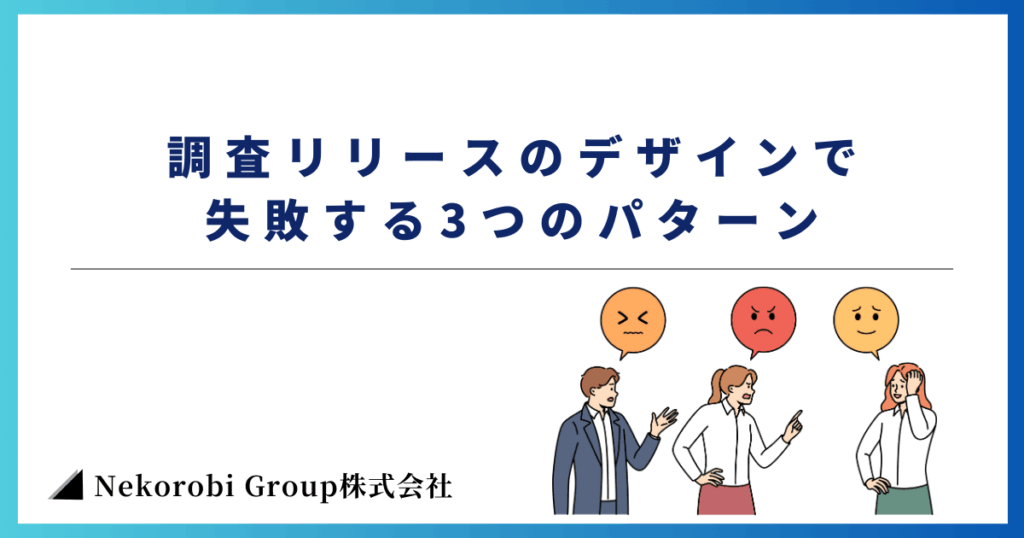
多くの企業が調査リリースで失敗する原因の一つが、デザインへの配慮不足です。どんなに貴重なデータを持っていても、見た目が素人っぽければ「信頼できない情報」として扱われてしまいます。実際に、メディア関係者は1日に数十件のプレスリリースを確認するため、第一印象で「読む価値があるか」を判断しています。
パターン①:グラフが読みにくい
最も多い失敗パターンはグラフが読みにくいことです。エクセルで作ったままの単調なグラフや、色使いが地味すぎるグラフでは、せっかくのデータの魅力が半減してしまいます。
具体的な問題例として、円グラフで青系の色ばかりを使って項目の区別がつかない、棒グラフの数値が8ポイントの小さな文字で印刷すると読めない、グラフタイトルが「質問1の結果」のような無味乾燥な表現になっている、といったケースが挙げられます。
また、グラフの背景に企業カラーを使いすぎて、肝心のデータが見えにくくなっているケースも頻繁に見られます。メディア関係者は「パッと見て3秒で理解できない」グラフは飛ばしてしまうため、視認性を最優先に考える必要があります。
パターン②:情報の詰め込みすぎ
二つ目の失敗は情報の詰め込みすぎです。「せっかく100万円かけて調査したのだから、すべてのデータを載せたい」という気持ちは理解できますが、一つのリリースに20個も30個もグラフを掲載すると、かえって何が重要なのかが分からなくなります。
実際に失敗した事例では、A4用紙10ページにわたって調査結果を羅列し、文字サイズが10ポイント以下になってしまい、結果として誰にも読まれない資料になってしまったケースがあります。読み手の集中力は限られているため、「最も伝えたいメッセージ3つ」に絞り込むことが重要です。
また、専門用語や業界用語を多用しすぎて、一般読者には理解困難な内容になってしまうことも多々あります。例えば、IT関連の調査で「DXのROI向上による業務プロセスの最適化」といった表現ではなく、「デジタル化で作業時間が半分に短縮」といった分かりやすい表現を心がけるべきです。
パターン③:企業色の出しすぎ
三つ目は企業色の出しすぎです。調査リリースの目的は客観的な情報提供ですが、自社のロゴを大きく表示しすぎたり、商品の宣伝色が強すぎたりすると、読み手に「結局は宣伝目的なのか」という印象を与えてしまいます。
典型的な失敗例として、ヘッダーに会社ロゴを大きく配置し、各ページに商品の写真を掲載し、最後に「詳しくは弊社商品をご利用ください」という露骨な宣伝文を入れるといったケースがあります。このような調査リリースは、メディアからは「広告」として扱われ、記事化される可能性が大幅に下がってしまいます。
適切なバランスとしては、企業名は小さく控えめに表示し、商品名は一切出さず、調査データそのものに価値を感じてもらうことで、結果的に「この会社は信頼できる情報を発信している」という印象を与えることです。
調査リリースで重要な「グラフデザイン」の基本ルール
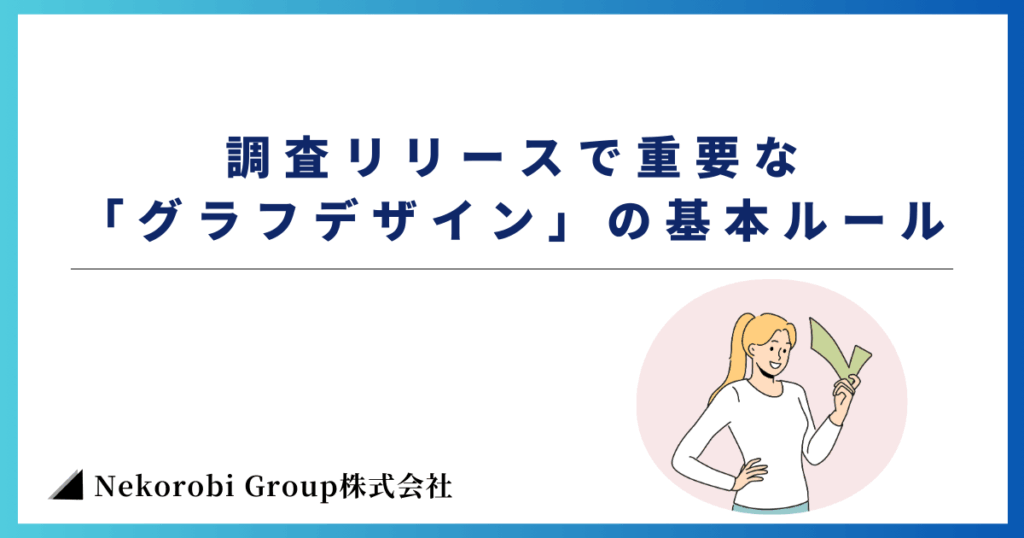
調査リリースの核となるのがグラフです。同じデータでも、グラフの作り方次第で読み手の印象は180度変わります。プロが作ったグラフと素人が作ったグラフの差は、色使いや配置などの細かいルールの違いにあります。
色使いの原則
色使いの原則では、まず使用色数を3〜4色程度に抑えることが基本です。虹色のように多色を使うと、かえって見づらくなってしまいます。
具体的な色選びのルールとして、重要なデータには暖色系(赤・オレンジ・黄色)を使い、補足データには寒色系(青・緑・紫)を使います。例えば、「賛成」「反対」「どちらでもない」の3択アンケートでは、賛成を緑、反対を赤、どちらでもないをグレーにするといった直感的に理解できる色分けが効果的です。
また、色覚特性に配慮したカラーパレットの使用も重要です。赤と緑の組み合わせは色覚に配慮が必要なため、赤と青、またはオレンジと青といった組み合わせを選ぶことで、より多くの人に正確に情報を伝えることができます。背景色は白またはごく薄いグレーに統一し、グラフ要素を際立たせることも大切なポイントです。
数値の表示方法
数値の表示方法では、まずグラフタイトルを分かりやすく設定します。「アンケート結果1」ではなく「テレワーク継続希望に関する意識調査(n=1,200)」といったように、内容と規模が一目で分かるタイトルをつけます。
パーセンテージや具体的な数値は、グラフ内に12ポイント以上の大きさで表示し、印刷しても読みやすいサイズを確保します。円グラフでは各セクションに「45.2%」といった具体的な数値を記載し、棒グラフでは棒の上部または内部に数値を配置します。また、必要に応じて「約半数」「4人に1人」といった分かりやすい表現も併記することで、データの意味をより伝えやすくなります。
小数点以下の表示についても配慮が必要で、「45.67823%」のような細かすぎる数値ではなく、「45.7%」程度に丸めることで読みやすさを向上させます。
サンプル数(N数)の表示
サンプル数(N数)の表示は、調査の信頼性を示すために必須の要素です。「N=1,000」または「n=1,000」といった形でグラフの下部に記載し、この調査がどの程度の規模で行われたものかを明示します。
信頼性の観点から、一般的に最低でも300〜500名以上の回答を得ることが望ましく、全国調査であれば1,000名以上のサンプルがあると説得力が増します。また、回答者の属性(「20-60代男女」「東京・大阪在住」「会社員対象」など)も併記することで、データの適用範囲を明確にできます。
複数の質問項目がある場合は、質問ごとに有効回答数が異なることがあるため、「全体n=1,000、有効回答n=987」といった形で表記することも重要です。
グラフの種類選び
グラフの種類選びでは、伝えたい内容に応じて最適な形式を選択します。全体に占める割合を示したい場合は円グラフまたはドーナツグラフ、複数項目の数値比較には横棒グラフまたは縦棒グラフ、時系列の変化には折れ線グラフを使用するのが基本です。
円グラフを使用する際は、項目数を5つ以下に抑え、最も重要な項目を12時の位置から時計回りに配置します。棒グラフでは、項目の並び順を数値の大きい順にすることで、ランキング要素を視覚的に表現できます。
また、比較を強調したい場合は、対比する要素を隣り合わせに配置したり、異なる色で明確に区別したりすることで、メッセージをより効果的に伝えることができます。複雑すぎるグラフ(3D効果や過度な装飾)は避け、シンプルで分かりやすいデザインを心がけることが重要です。
調査リリースの「タイトルデザイン」で注目度を上げる方法
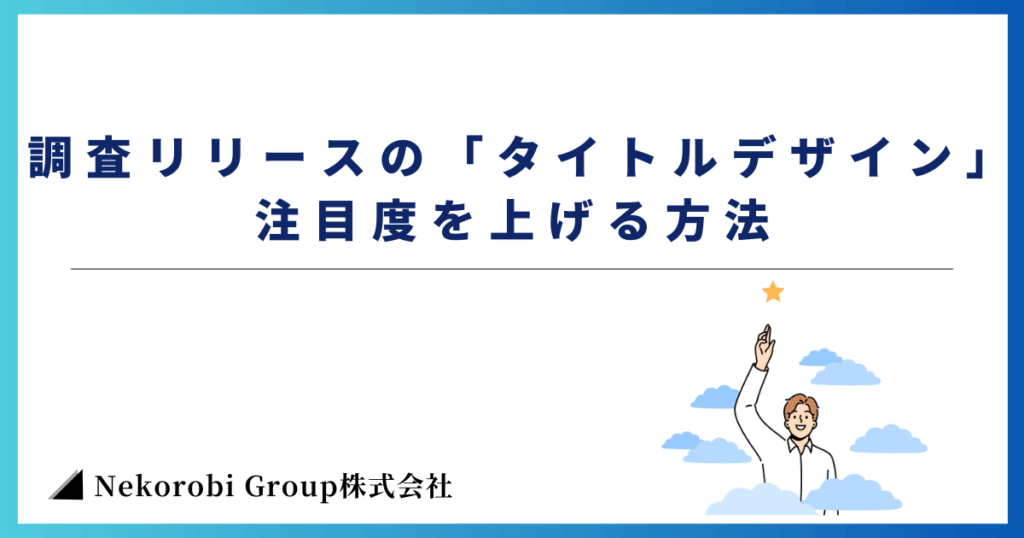
調査リリースの第一印象を決めるのがタイトルデザインです。メディア関係者が最初に目にする部分でもあり、ここで興味を引けなければ本文を読んでもらえません。
数字の効果的な見せ方
数字の効果的な見せ方が重要なポイントです。「85%の人が○○と回答」といった具体的な数字は、タイトル内で最も目立つように表示します。数字部分だけフォントサイズを大きくしたり、色を変えたりすることで、インパクトを与えることができます。また、「約8割」よりも「78.3%」といったように、具体的な数値を使うことで調査の精密さをアピールできます。
フォント選びのルール
フォント選びのルールも見た目の印象を大きく左右します。タイトルには読みやすさを重視したゴシック体を使用し、装飾的すぎるフォントは避けるのが基本です。また、文字のサイズにメリハリをつけることで、情報の重要度を視覚的に伝えることができます。メインタイトルは大きく、サブタイトルは一回り小さく、調査概要はさらに小さくといった階層構造を意識します。
キーワードの強調方法
キーワードの強調方法も工夫が必要です。調査結果の中で最も注目すべき部分を「」で囲んだり、色を変えたりして強調します。例えば『「リモートワーク継続希望」が9割超え』といった形で、話題性のある部分を際立たせることで、読み手の関心を引くことができます。
タイトルの長さの調整
タイトルの長さにも注意が必要です。あまり長すぎると読みづらくなるため、メインタイトルは30〜50文字程度に収めるのが理想的です。どうしても情報を盛り込みたい場合は、サブタイトルを活用して情報を整理します。
調査リリースの「全体レイアウト」で信頼性を演出するコツ
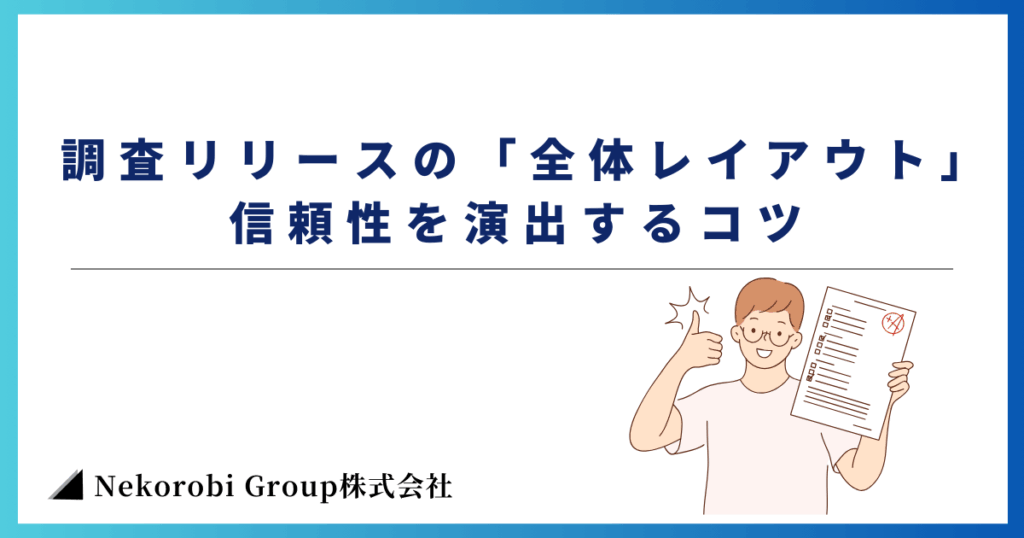
プロフェッショナルな印象を与える全体レイアウトの構築は、調査リリースの信頼性に直結します。読み手が「この調査は信頼できる」と感じるようなデザインを心がける必要があります。
情報の視覚的階層を明確にすることが最も重要です。タイトル、調査概要、主要結果、詳細データ、会社情報といった順序で情報を整理し、それぞれの重要度に応じてフォントサイズや色を調整します。読み手が上から下へスムーズに情報を処理できるような流れを作ることで、内容への理解度が格段に向上します。
余白の効果的な活用もプロっぽさを演出する重要な要素です。情報を詰め込みすぎず、適切な余白を設けることで、洗練された印象を与えることができます。特にグラフと文章の間、段落と段落の間には十分な余白を設け、読みやすさを向上させます。また、ページの端から端まで文字を配置するのではなく、左右に余白を設けることで、読み手の目の負担を軽減できます。
統一感のあるデザインを保つことも重要です。使用するフォント、色合い、線の太さなどを統一し、リリース全体が一つの資料として完成されている印象を与えます。ランダムに色や書体を変えると、かえって素人っぽい印象を与えてしまうため注意が必要です。
企業ロゴの配置については、控えめに、しかし確実に企業名が分かるように配置します。一般的には、ヘッダー部分の右上か左上に小さめに配置し、フッター部分に会社概要を記載するパターンが多く使われています。調査の客観性を保ちつつ、発信元を明確にするバランスが重要です。
調査リリースのデザイン事例から学ぶ「成功パターン」
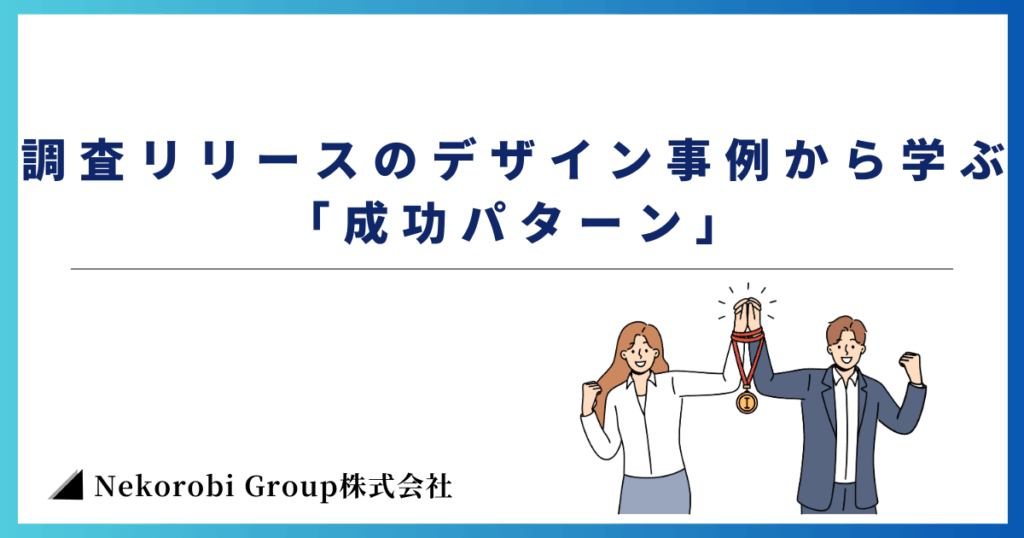
実際に話題になった調査リリースのデザインには、いくつかの共通する成功パターンがあります。これらのパターンを理解することで、自社でも応用できるヒントが見つかります。
シンプルで分かりやすいグラフを使用している事例では、一目で内容が理解できるような工夫が施されています。例えば、働き方に関する調査では、「在宅勤務希望者」を青、「出社希望者」を赤といったように、直感的に理解できる色分けを行っています。また、円グラフでは最も重要な項目を12時の位置から開始し、時計回りに重要度順に配置するといった配慮も見られます。
ストーリー性のあるレイアウトも成功事例の特徴です。単純にデータを羅列するのではなく、「問題提起→調査結果→考察→今後の展望」といった流れで構成することで、読み手を最後まで引き込むことができます。この際、各セクションごとに小見出しを設け、読み手が途中で離脱しないような工夫を行っています。
業界特性を活かしたデザインも注目すべきポイントです。IT関連企業では先進的でスタイリッシュなデザイン、医療関連では清潔感と信頼性を重視したデザイン、教育関連では親しみやすさを重視したデザインといったように、業界のイメージに合わせたデザインを採用することで、より強い印象を与えています。
中小企業でも真似できる工夫として、既存のデザインテンプレートを上手に活用している例が多く見られます。完全にオリジナルでデザインを作成するのではなく、プロが作成したテンプレートをベースに、自社の色合いやロゴを適用することで、コストを抑えながらも洗練されたデザインを実現しています。
調査リリースのデザインを外注する際の注意点
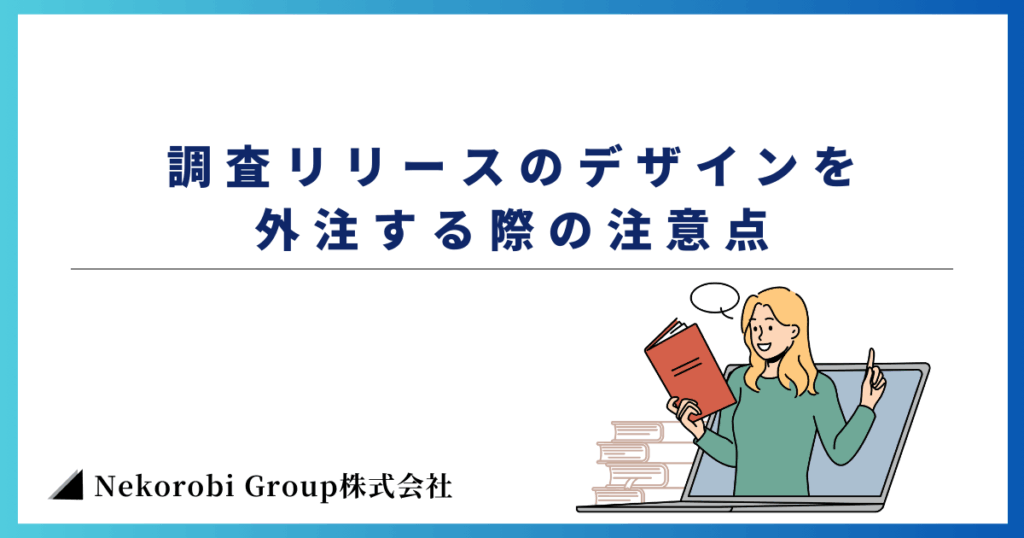
調査リリースのデザインをプロに依頼する際には、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。適切な依頼方法と明確な指示により、期待通りの成果物を得ることができます。
デザイナーとの事前打ち合わせでは、調査の目的、ターゲット読者、期待する効果について詳しく説明します。単に「かっこよく作ってください」ではなく、「信頼性を重視したい」「話題性を前面に出したい」といった具体的な方向性を伝えることが重要です。また、他社の参考事例があれば、それを見せながら「このような雰囲気で」という指示をすることで、認識のズレを防ぐことができます。
費用相場と品質のバランスについて理解しておくことも大切です。調査リリースのデザイン費用は、シンプルなものであれば5万円程度から、凝ったデザインであれば20万円以上になることもあります。ただし、高額な費用をかければ必ず良い結果が得られるとは限りません。自社の予算と目的に応じて、最適なレベルのデザインを選択することが重要です。
修正回数と納期の取り決めも事前に明確にしておきます。通常、デザイン制作では2〜3回の修正が含まれることが多いですが、それを超える修正には追加費用が発生する場合があります。また、調査データの集計完了から配信までのスケジュールを逆算し、十分な制作期間を確保することで、品質の高い成果物を得ることができます。
広報代行会社との連携を検討している場合は、デザイン制作から配信まで一貫してサポートしてもらえるかを確認します。デザインだけでなく、メディアリストの作成、配信タイミングの調整、効果測定まで含めたトータルサポートを受けることで、より効果的な調査リリースの展開が可能になります。
まとめ
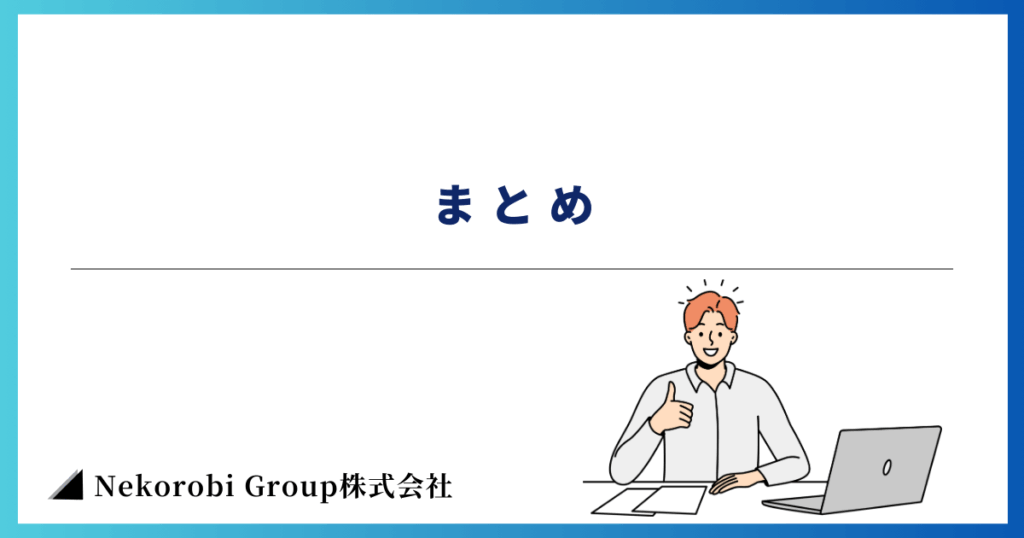
調査リリースは、中小企業にとって大きな可能性を秘めたPR手法です。特にデザインの力を借りることで、大手企業にも負けない注目度の高い情報発信が可能になります。しかし、効果的な調査リリースを作成するには、調査の企画から実施、デザイン制作、配信まで、多くの専門的な知識とスキルが必要です。
自社ですべてを行うのは現実的ではありませんが、基本的な知識を持っておくことで、プロとの協業をより効果的に進めることができます。まずは信頼できる広報の専門家に相談し、自社に最適な調査リリースの戦略を検討してみることをおすすめします。適切なパートナーと組むことで、調査リリースは御社の認知度向上と信頼性構築に大きく貢献するツールとなるでしょう。