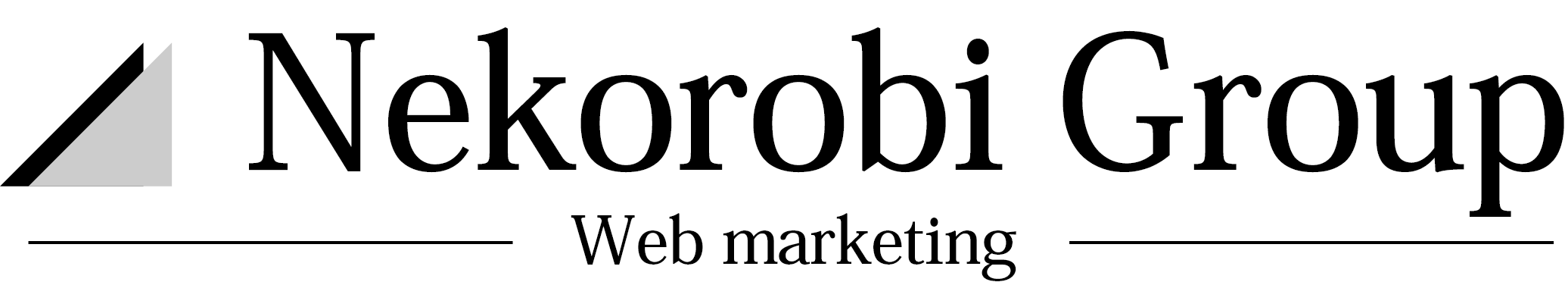「何度プレスリリースを配信しても、メディアに取り上げられない」「時間をかけて作成したのに、まったく反応がない」
そんな経験から「プレスリリースって意味ないのでは?」と感じている広報担当者の方は少なくありません。しかし、その認識は大きな誤解かもしれません。
実際には、適切な方法で配信されたプレスリリースの記事化率は70%を超えるというデータもあります。成果が出ないのは、プレスリリース自体に問題があるのではなく、作成方法や配信方法に改善点があるからです。
本記事では、プレスリリースで成果が出ない根本原因を明確にし、すぐに実践できる改善方法を具体的に解説します。「意味のない」プレスリリースを「価値ある」広報ツールに変える方法をお伝えします。
プレスリリースが「意味ない」と感じる3つの根本原因
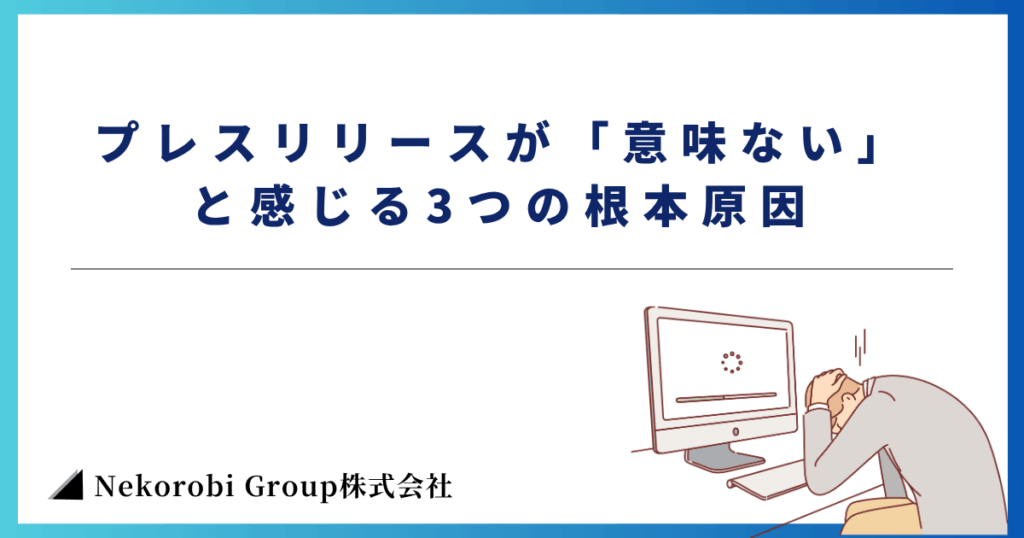
プレスリリースで成果が出ない企業に共通する問題は、主に以下の3つに集約されます。それぞれの原因を具体例とともに詳しく見ていきましょう。
原因1:メディアが求める「ニュース価値」を理解していない
最も多い失敗パターンが、企業が伝えたい情報とメディアが求める情報のミスマッチです。
多くの企業では、新商品のスペック情報のみに焦点を当てたプレスリリースを作成しがちです。例えば「当社の新商品は、従来品より20%性能が向上しました」というような内容です。しかし、このような技術仕様の羅列は、企業にとっては重要な情報でも、メディアにとってはニュース価値が低いと判断されてしまいます。
また、企業の歴史や創業者の想いを中心としたプレスリリースも見受けられます。「創業100年の歴史を持つ当社が、新たな挑戦を始めます」といった内容は、企業のアイデンティティを表現する重要な要素ですが、読者や記者が求める具体的なメリットや価値が伝わらないという問題があります。
さらに深刻なのは、単なる業務連絡レベルの内容をプレスリリースとして配信してしまうケースです。「夏季休暇のお知らせ」「店舗移転のご案内」「人事異動の発表」などは、企業運営上は必要な情報ですが、一般の読者やメディアにとってはニュース価値がほとんどありません。
メディアが真に求めているのは、新規性(業界初、世界初などの希少価値)、社会性(社会問題の解決、トレンドとの関連性)、影響性(多くの人に影響を与える内容)、季節性(タイムリーな話題性)、人間性(感動やストーリー性のある内容)といった要素を含んだ情報です。これらの要素を理解せずにプレスリリースを作成することが、成果が出ない最大の原因となっています。
原因2:配信方法と配信先の選定ミス
2つ目の問題は、「誰に」「どのように」配信するかの戦略不足です。
よくある配信ミスとして、メディアの特性を無視した無差別配信が挙げられます。IT系のニュースサイトに飲食店の新メニュー情報を配信したり、スポーツ部門にビジネス系の話題を送付したりするケースです。また、全国紙に地域限定のイベント情報を配信するなど、媒体の影響範囲と情報の対象範囲がマッチしていない場合も多く見られます。
さらに深刻なのは、メディアリストの管理不足です。退職した記者に送り続けたり、部署異動により担当が変わった記者に従来通り送付したりすることで、適切な担当者に情報が届かない状況が発生します。このような「無差別配信」は、メディア関係者から敬遠される原因となり、今後のプレスリリースも読まれなくなるリスクを高めます。
適切な配信を行うためには、メディアの読者層と自社のターゲット層の一致度、過去の掲載記事の傾向分析、担当記者の専門分野の把握、媒体ごとの締切やリードタイムの理解といった要素を総合的に検討する必要があります。しかし、多くの企業ではこれらの調査や分析が不十分なまま配信を行っているため、効果的なアプローチができていないのが現状です。
原因3:効果測定の方法が間違っている
3つ目の問題は、プレスリリースの効果を正しく測定できていないことです。
多くの企業が「記事掲載数」のみで効果を判断していますが、プレスリリスの真の価値はもっと多面的です。短期的な掲載結果のみに着目していると、プレスリリースの本当の価値を見逃してしまいます。
見落としがちな効果として、認知度向上があります。ブランド名の検索数増加や、企業名での指名検索の増加は、直接的な売上にはすぐに結びつかないものの、中長期的なブランド価値向上に大きく寄与します。信頼性向上も重要な効果で、第三者であるメディアによる情報発信は、企業の広告よりも高い信頼性を持ちます。
SEO効果も軽視されがちですが、被リンク獲得によるWebサイト評価向上は、長期的な集客力向上につながります。営業機会創出では、メディア掲載をきっかけとした問い合わせ増加や商談機会の創出が期待できます。採用力強化として、企業情報の露出による優秀な人材獲得効果も見逃せません。投資家へのアピールとして、事業の成長性や将来性を訴求する効果もあります。
これらの多面的な効果を測定せず、単純な掲載数のみで判断することが、「プレスリリースは意味がない」という誤解を生む原因となっています。適切な効果測定により、プレスリリースの真の価値を正しく評価することが重要です。
プレスリリースで意味のある”成果”を出すための5ステップ
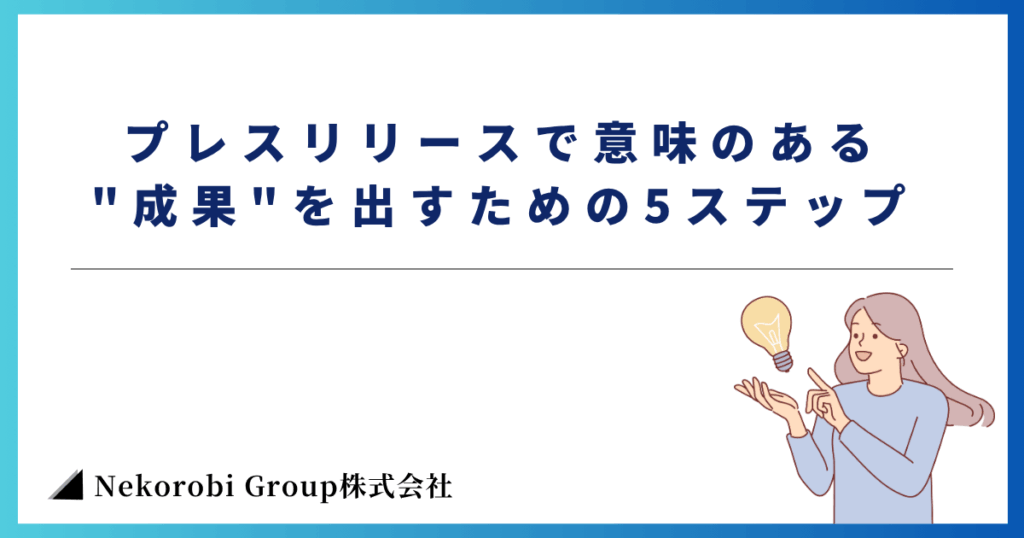
ここからは、具体的な改善方法を5つのステップに分けて解説します。これらのステップを順番に実践することで、プレスリリースの効果を劇的に向上させることができます。
ステップ1:ニュース価値のある「切り口」を見つける方法
商品やサービスそのものではなく、「なぜ今なのか」「誰のためなのか」という切り口を見つけることが重要です。
まず社会課題との関連性を探ってみましょう。現在話題になっている社会問題と自社の商品・サービスがどのように課題解決に貢献するのかを明確にし、具体的な効果や数値で示せるかを検討します。次に、業界のトレンドキーワードや消費者の行動変化との接点を見つけ、時代の変化にどう対応しているかを整理します。
さらに、「初」「最大」「唯一」の要素がないかを探すことも効果的です。業界初の取り組み、最大規模や最高品質の要素、唯一の技術や手法を使っている点などは、メディアが注目しやすいポイントになります。
例えば、悪い例として「新しいスマートフォンアプリをリリースしました」という発表があります。これを改善すると「高齢者の孤独死を防ぐ見守りアプリ、コロナ禍で需要急増を受け無料提供開始」となり、社会課題、時流、ターゲットが明確になり、メディアが取り上げやすい内容に変わります。
ステップ2:記者が読みたくなるタイトル・構成のルール
プレスリリースの成否は、タイトルで8割決まると言っても過言ではありません。記者は1日に数百件のプレスリリースを目にするため、タイトルで興味を引けなければ本文を読んでもらえません。
効果的なタイトルを作成するには、まず30文字以内で完結させることが重要です。長すぎるタイトルは最後まで読まれず、スマートフォンでも読みやすい文字数に調整する必要があります。具体的な数字を含めることも効果的で、「大幅に」を「50%」に、「多くの」を「1万人の」に変更するだけで説得力が増します。
ターゲットを明確にすることも重要で、「働く女性向け」「中小企業経営者専用」など、読み手が自分事として捉えられる表現を使います。機能説明ではなく、利用者が得られる価値(時間短縮、コスト削減、課題解決)をベネフィットとして前面に出し、「なぜ○○が選ばれるのか?」「ついに実現!」などの疑問形や感嘆符を活用することで、読者の興味を引くことができます。
プレスリリースの基本構成は、発信者情報(会社名、発信日)から始まり、タイトル(30文字以内、ニュース価値を明確に)、リード文(5W1Hを含む200文字程度の要約)、本文(背景→内容→今後の展開の順序)、会社概要・問い合わせ先の順序で構成します。
ステップ3:適切な配信先の選定と配信タイミング
闇雲に多くのメディアに送るより、適切なメディアに絞って配信する方が効果的です。
メディア選定では、まず自社の業界を扱う専門メディア、ターゲット顧客が読む一般メディア、地方展開の場合は地域メディアをリストアップします。次に各メディアの特性を調査し、掲載記事の傾向分析、読者層の把握、更新頻度と締切の確認を行います。
さらに担当記者を特定し、過去記事の執筆者確認、専門分野の把握、SNSでの発信内容をチェックすることで、より精度の高いアプローチが可能になります。
配信タイミングも重要な要素です。曜日では火曜から木曜が最も読まれやすく、月曜は週末の情報整理で忙しく、金曜は週末モードで注意散漫になりがちです。時間帯では、朝の情報収集時間である10:00〜11:00と、午後の作業開始時間である14:00〜15:00が効果的です。
媒体別のリードタイムも考慮する必要があり、Web媒体は当日から3日前、新聞は1週間前、雑誌は1〜2ヶ月前の配信が適切です。これらのタイミングを把握して配信することで、メディアに取り上げられる確率を高めることができます。
ステップ4:効果的なプレスリリースの配信頻度
配信頻度は「質」を保てる範囲で「継続性」を重視することが重要です。
推奨される配信頻度は、スタートアップ企業が月1〜2回、中小企業が月1回、大企業が週1〜2回程度です。この頻度を守ることで、メディアとの関係構築、企業の信頼性向上、ネタの蓄積という3つのメリットを得ることができます。
定期的な接触により記者との関係性が構築され、継続的な情報発信により企業の透明性をアピールできます。また、過去のプレスリリースが記事作成時の参考資料として活用されることもあります。
配信頻度を保つためには、商品・サービスリリース以外のネタも活用することが重要です。社会貢献活動、社内の取り組み、業界動向への見解、季節イベントや記念日との関連付け、他社との提携やコラボレーション、調査レポートや統計データの発表など、多様なネタを準備することで継続的な配信が可能になります。
ステップ5:正しい効果測定と改善サイクルの作り方
プレスリリースの効果は多角的に測定し、継続的に改善していくことが重要です。
測定すべき指標は5つのカテゴリーに分類されます。直接的効果として、記事掲載数(Web、紙媒体別)、記事のPV数やシェア数、広告換算値(掲載記事を広告で出稿した場合の費用)を測定します。間接的効果では、企業名・商品名の検索数増加、公式サイトへの流入数増加、SNSでの言及数増加を追跡します。
ビジネス効果として、問い合わせ数増加、商品・サービスの売上向上、新規顧客獲得数を測定し、ブランド効果では、ブランド認知度の向上、企業イメージの改善、採用応募者数の増加を評価します。SEO効果として、被リンク数の増加、検索順位の向上、オーガニック流入の増加も重要な指標です。
改善サイクルの実践では、月次レビューで上記指標の数値を確認し、四半期分析でトレンドと改善点を抽出し、年次戦略見直しで全体的な方向性を調整します。このサイクルを継続することで、プレスリリースの効果を継続的に向上させることができます。
プレスリリースの代替案:他の広報・PR手法との使い分け

プレスリリースが自社に適さない場合や、他の手法と組み合わせたい場合の選択肢を紹介します。重要なのは、それぞれの手法の特徴を理解し、自社の目的や状況に最適な組み合わせを見つけることです。
SNSマーケティングとの組み合わせ戦略
プレスリリースとSNSマーケティングは、それぞれ異なる役割を持ちながらも、効果的に組み合わせることで相乗効果を生み出すことができます。
プレスリリース配信後のSNS活用では、記事が掲載された際の拡散施策が重要になります。記事掲載を知らせる投稿を作成し、フォロワーに情報をシェアしてもらうことで、より広い層にリーチできます。また、プレスリリースの内容をSNS向けにアレンジし、より親しみやすい表現や視覚的なコンテンツに変換することで、SNSユーザーの関心を引くことができます。
インフルエンサーとの連携も効果的な手法です。プレスリリースで公式発表を行った後、関連分野のインフルエンサーに商品やサービスを体験してもらい、自然な形で情報を拡散してもらうことで、より信頼性の高い情報発信が可能になります。
使い分けの基準として、プレスリリースは公式発表や信頼性を重視する場面で活用し、SNSは日常的な情報発信や双方向のコミュニケーションを図る際に活用することが効果的です。
オウンドメディアとプレスリリースの相乗効果
オウンドメディアとプレスリリースをうまく組み合わせると、「記事掲載で終わらせない広報」が実現できます。単発の話題づくりではなく、継続的に見込み客との接点を持てる情報発信が可能になるのです。
たとえばプレスリリースを配信する前に、オウンドメディアで開発ストーリーや担当者インタビューを公開しておけば、リリースがメディアに取り上げられた際、「もっと知りたい」という読者を確実に自社サイトへ誘導できます。これは、メディア掲載→自社への流入→信頼獲得という導線をつくる強力な施策です。
また、プレスリリースでは字数制限やフォーマットの関係で語りきれない技術的なこだわりや活用事例を、リリース後にオウンドメディアでフォローすれば、専門性の高い読者層や検討フェーズにある顧客を深く惹きつけることができます。
さらに、記事掲載後には「反響まとめ」や「掲載メディア一覧」をオウンドメディアで紹介するのもおすすめです。第三者評価を見せることで自社の信頼性を補強でき、営業資料やSNS投稿にも活用可能になります。
- 読者のベネフィット(例:見込み客の導線設計、信頼獲得、営業活用)を明記
- 「たとえば」「おすすめ」など具体的なアクション例を入れる
- 「終わらせない広報」など印象に残るフレーズを差し込む
インフルエンサー活用との使い分け
プレスリリースとインフルエンサーマーケティングは、それぞれ異なる特徴を持っており、目的に応じて使い分けることが重要です。
プレスリリースは企業からの公式情報として位置づけられ、長期的な信頼構築に適しています。一方、インフルエンサーマーケティングは個人的な推奨という形で情報が伝わるため、短期的な認知拡大や親近感の醸成に効果的です。
効果的な組み合わせの流れとして、まずプレスリリースで公式発表を行い、企業としての正式な情報発信を実施します。その後、関連分野のインフルエンサーに実際に商品やサービスを体験してもらい、率直なレビューや感想を発信してもらいます。最終的に、プレスリリースによる公式性とインフルエンサーによる親近感の両方の効果を合わせることで、総合的な認知度向上を図ることができます。
重要なのは、それぞれの手法の特性を理解し、自社の目標達成に最も効果的な組み合わせを見つけることです。
プレスリリースが「意味ないもの」から脱却した成功例
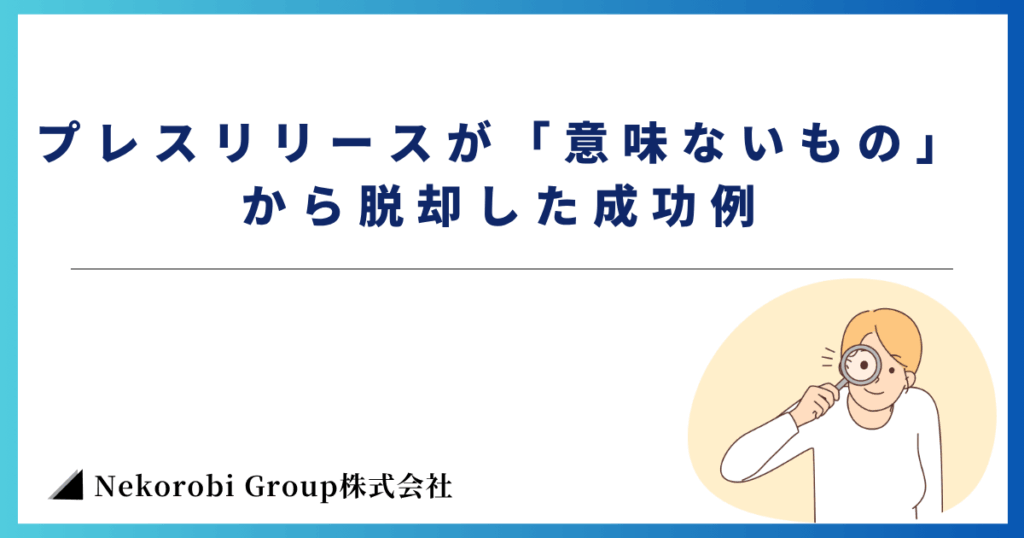
実際にプレスリリースの改善により成果を上げた企業の事例を紹介します。これらの事例から、具体的な改善ポイントと成果を学ぶことができます。
事例1:スタートアップ企業の初回掲載成功パターン
設立2年目のAIスタートアップ(従業員15名)の事例です。この企業は当初、技術説明に終始したプレスリリースを5回配信しましたが、一度も掲載されることがありませんでした。担当者は「プレスリリースは意味がない」と判断する寸前まで追い込まれていました。
改善のポイントは3つありました。まず切り口を大幅に変更し、「AIアルゴリズム開発」という技術的な内容から「中小企業の人手不足解決」という社会課題にフォーカスした内容に変更しました。次に具体的数値を追加し、単に「効率化」と表現していた部分を「作業時間を80%短縮」と具体化しました。さらに社会課題との関連付けを強化し、コロナ禍での働き方改革ニーズに対応していることを明確に打ち出しました。
その結果、改善後初回の配信で業界専門メディア3社が記事として取り上げ、Web記事のPV数は合計5万回に達しました。最も重要な成果として、問い合わせ数が前月比300%増加し、実際のビジネス機会創出につながりました。
事例2:中小企業の継続配信で認知度向上を実現
創業50年の製造業(従業員80名)の事例では、継続配信の重要性が証明されました。この企業は従来、年1〜2回の不定期配信を行っており、内容も商品カタログのような技術仕様の羅列が中心でした。当然ながら、メディア掲載実績はほぼゼロの状態が続いていました。
改善では3つの要素に注力しました。配信頻度を年2回から月1回の定期配信に変更し、メディアとの接触機会を大幅に増やしました。ネタの多様化も図り、商品情報以外に社会貢献活動、技術解説、業界動向への見解なども追加しました。さらに、地元新聞や地域経済誌を中心とした地域メディアへの重点的アプローチを開始しました。
6ヶ月間の継続的な取り組みの結果、地域メディアでの掲載が15件に達し、地元企業としての認知度が大幅に向上しました。特に注目すべき成果は、新卒採用応募者数が前年比200%増加したことです。これは、継続的なメディア露出により企業の存在感が高まり、就職活動中の学生の目に留まりやすくなったためと分析されています。
事例3:配信方法改善で記事化率70%を達成した事例
上場企業の新規事業部門では、配信方法の最適化により劇的な改善を実現しました。当初は500媒体への大量一斉配信を行っていましたが、記事化率は10%程度に留まり、配信コストに見合わない効果に悩んでいました。
改善アプローチは3段階で実施されました。まず配信先を500媒体から50媒体に厳選し、質の高いメディアに集中することにしました。次に個別アプローチを強化し、重要メディアには配信前に内容の事前説明を実施するようになりました。さらに配信タイミングを最適化し、各媒体の特性や締切に合わせて個別にタイミングを調整しました。
この取り組みにより、記事化率が70%に大幅改善されました。同時に配信コストを60%削減することにも成功し、費用対効果が大幅に向上しました。最も重要な成果は、質の高い媒体での掲載が増加し、より影響力のある情報発信が可能になったことです。この事例は、量より質を重視したアプローチの有効性を示しています。
プレスリリースを続けるべきか判断する3つの基準
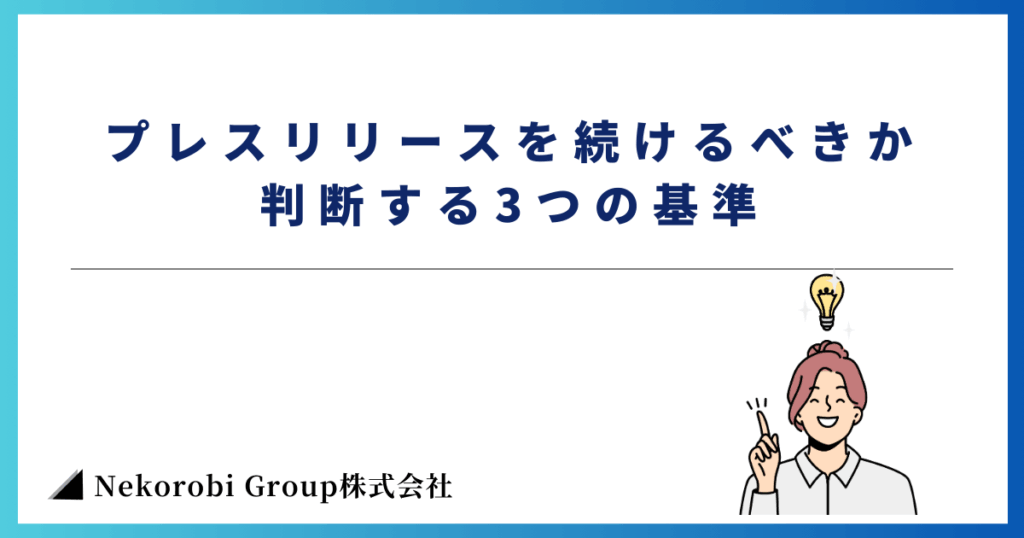
すべての企業にプレスリリースが適しているわけではありません。以下の基準で継続の判断をしてください。自社の状況を客観的に評価し、最適な広報戦略を選択することが重要です。
基準1:自社の商品・サービスのニュース性
プレスリリースの継続を推奨できるのは、業界の技術革新に関わる商品・サービスを提供している場合です。社会課題解決に寄与する内容であれば、メディアの関心を引きやすく、記事化される可能性が高くなります。また、ターゲット層が明確で市場規模が大きく、定期的に新しい取り組みを行っている企業であれば、継続的にネタを提供できるため、プレスリリースの効果を期待できます。
一方で、既存商品の小幅な改良のみを繰り返している場合や、ニッチすぎてメディアの関心を引きにくい分野の場合は、プレスリリースの見直しを検討する必要があります。新しい取り組みを行う頻度が低い企業についても、無理にプレスリリースを継続するよりも、他の広報手法を検討した方が効果的かもしれません。
自社の商品・サービスがメディアにとってニュース価値があるかを客観的に評価し、継続の判断を行うことが重要です。
基準2:投資できるリソースと期待する成果のバランス
プレスリリースを継続するために必要なリソースを正確に把握することが重要です。月次ベースで必要なリソースとして、作成時間が10〜20時間、配信費用が5万円〜15万円、効果測定時間が5〜10時間程度を見込む必要があります。
一方で期待できる成果については、短期(1〜3ヶ月)では認知度向上や問い合わせ増加、中期(3〜6ヶ月)ではSEO効果や営業機会創出、長期(6ヶ月〜)ではブランド価値向上や採用力強化などが挙げられます。
このリソースと成果のバランスを評価し、自社の経営状況や事業優先度と照らし合わせて判断することが重要です。投入できるリソースに対して期待する成果が見合わない場合は、他の手法を検討することをおすすめします。特にスタートアップ企業などリソースが限られている場合は、より効果が期待できる手法に集中することも重要な判断です。
基準3:他の広報施策との優先順位
プレスリリースの優先度が高いのは、BtoB企業で企業の信頼性が重要な場合です。新規事業立ち上げで認知度向上が急務の企業や、採用強化が経営課題となっている企業についても、プレスリリースによる効果が期待できます。これらの企業では、第三者であるメディアからの情報発信による信頼性向上の効果が特に大きくなります。
一方で、他施策の優先度が高い場合もあります。BtoC企業でSNSマーケティングの効果が既に実証されている場合や、インフルエンサーマーケティングで成果実績がある場合は、そちらに重点を置く方が効果的かもしれません。オウンドメディアの読者が十分に多く、直接的な情報発信で十分な効果が得られている場合も同様です。
重要なのは、限られたリソースの中で最も効果的な施策に集中することです。プレスリリースありきで考えるのではなく、自社の目標達成に最も適した手法を選択し、必要に応じて組み合わせを検討することが大切です。
まとめ:プレスリリースを「意味ある」施策に変える行動プラン

「プレスリリースは意味がない」と感じているなら、それは方法論の問題であり、プレスリリース自体の問題ではありません。適切な改善を行うことで、プレスリリースは企業の成長を大きく加速させる強力なツールに変わります。
今すぐ実践できる改善アクションを段階的に整理しました。まず今週実践することとして、過去のプレスリリースのタイトルを見直し、ニュース価値の要素が含まれているかをチェックしてください。配信先メディアリストを整理し、適切でない配信先を削除することも重要です。さらに効果測定指標を再定義し、記事掲載数だけでなく多角的な評価基準を設定しましょう。
今月実践することとしては、社会課題やトレンドと自社の取り組みの関連性を整理することから始めます。ターゲットメディアの過去記事を分析し、どのような内容が求められているかを把握してください。そして継続的な配信スケジュールを立案し、質を保ちながら定期的に情報発信できる体制を構築しましょう。
今四半期実践することでは、改善されたプレスリリースを月1回以上継続配信し、実際の成果を測定します。効果測定結果をもとに内容や配信方法を継続的に改善し、必要に応じて他の広報手法との組み合わせも検討してください。
重要なのは、短期的な成果に一喜一憂せず、継続的な改善を重ねることです。プレスリリースは正しく活用すれば、企業の信頼性向上、認知度拡大、営業機会創出など、多面的な効果をもたらします。諦めずに改善を続けることで、必ず「意味のある」成果を実感できるはずです。
まずは本記事で紹介した改善ステップの中から、実践しやすいものから始めてみてください。小さな改善の積み重ねが、やがて大きな成果につながることを確信しています。