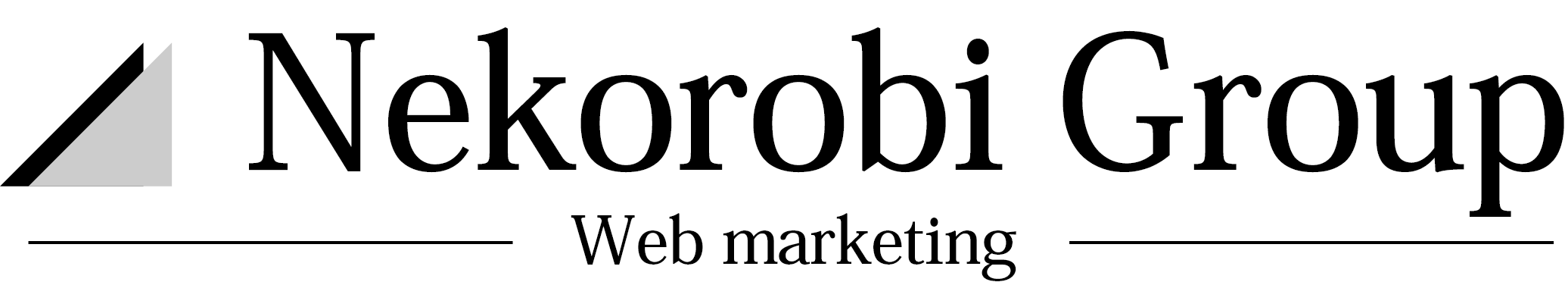「新商品を発表したいけど、プレスリリースってどう書けばいいの?」
「メディアに取り上げてもらえるプレスリリースの書き方が分からない」
中小企業の社長として、このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
プレスリリースは、自社の情報を効果的にメディアや顧客に伝える重要な広報手段です。しかし、ただ情報を羅列するだけでは、数多くのプレスリリースの中に埋もれてしまい、メディアに取り上げられることはありません。
実は、メディアに注目されるプレスリリースには、書き方にいくつかの共通したポイントがあります。基本的な構成を理解し、効果的な書き方のコツを押さえることで、あなたの会社のニュースも記者の目に留まりやすくなるでしょう。
この記事では、プレスリリースの書き方を基本構成から実践的なテクニックまで、例文を交えながら詳しく解説します。広報活動を成功に導くための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。
プレスリリースの書き方の基本構成を理解しよう
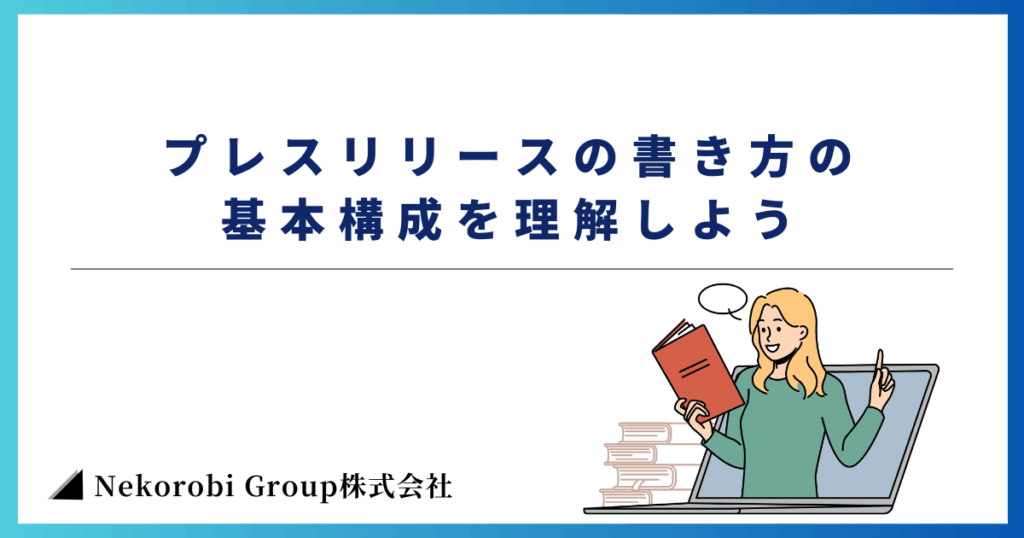
プレスリリースには、効果的に情報を伝えるための決まった構成があります。
メディア関係者が推奨するこの基本構成を理解することが、成功するプレスリリースの書き方の第一歩です。実際に、この構成に従って作成されたプレスリリースは、記事化率が70%を超えるという調査結果もあります。
プレスリリースの5つの基本要素
プレスリリースの成功は、タイトルから問い合わせ先まで、5つの要素がそれぞれの役割を果たすことで実現されます。
毎日数百通のプレスリリースを受け取る記者にとって、読みやすい構成は必須条件なのです。
タイトルと写真が最重要
タイトルはプレスリリースの「顔」となる最も重要な部分で、記者がまず最初に目にする箇所です。
例えば「AI搭載の新型掃除機、従来比30%の清掃効率向上を実現」のように、具体的な数値と技術を含めることで記者の関心を引きます。
写真・画像は視覚的に情報を伝える重要な要素で、文章だけでは伝わりにくい商品の魅力やイベントの様子を効果的に表現します。
リード文と本文の役割
リード文は、タイトルの次に重要な要約部分として、250〜300文字程度で全体の内容を簡潔にまとめます。
ここで5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、なぜ、どのように)の要素を含めることが重要です。
本文では、リード文で紹介した内容をより詳しく説明し、背景、詳細、社会的意義などを含めて読み手が理解しやすいよう構成します。
問い合わせ先の重要性
問い合わせ先は、メディアからの取材依頼や一般からの問い合わせに対応するための連絡先情報です。担当者に確実に繋がる連絡先を記載することで、取材機会を逃すリスクを避けられます。
携帯電話番号やメールアドレスなど、迅速に対応できる連絡手段を複数用意しておくことが理想的です。
全体的なレイアウトの考え方
プレスリリースは、忙しい記者が短時間で内容を把握できるよう、逆三角形の構造で情報を配置します。新聞の一面記事と同じように、最も重要な情報を冒頭に置き、詳細情報を後に続ける構成が基本となります。
例えば、大手食品メーカーが新商品を発表する際のプレスリリースでは、タイトルで「日本初の○○技術を活用したヨーグルト発売」と打ち出し、リード文で「健康志向の高まりを受け、腸内環境改善効果を30%向上させた」という具体的な数値を示します。
このような構成により、記者は短時間で「これは記事になる」と判断でき、結果的にメディア掲載の可能性が大幅に高まります。文字数の目安としては、A4サイズで1〜2枚程度(1000〜2000文字)が理想的とされています。
プレスリリースのタイトルの書き方のコツと例文
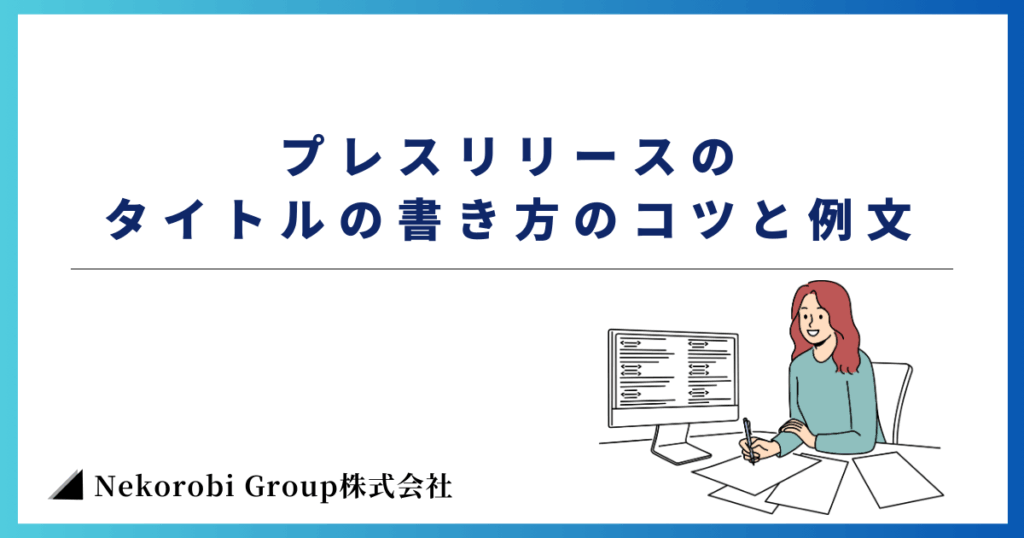
プレスリリースのタイトルは「9割を決める」と言われるほど重要な要素です。記者は毎日数十通、数百通のプレスリリースを目にするため、タイトルだけで読むかどうかを判断することがほとんどです。
実際に、大手PR会社の調査では、魅力的なタイトルを付けたプレスリリースの記事化率は、そうでないものの3倍以上になることが判明しています。
効果的なタイトルの書き方の3つの法則
タイトル作成には明確な法則があり、これを守ることで記者の注目を集めることができます。成功しているプレスリリースの多くは、この3つの法則を実践しています。
30文字以内で数字と固有名詞を活用
文字数は30文字以内を目安にし、具体的な数字や固有名詞を積極的に活用します。
例えば「新サービス開始のお知らせ」ではなく「AI翻訳サービス『○○トランス』、従来比80%の精度向上で3月開始」のように具体性を持たせます。
数字があることで客観性が増し、固有名詞があることで記憶に残りやすくなります。
ニュースバリューを前面に押し出す
「日本初」「業界最大」「○○%向上」など、報道価値の高いキーワードを含めることが重要です。ただし、これらの表現を使う際は必ず根拠となるデータを用意し、「自社調べ」でも構わないので裏付けを明確にしておく必要があります。記者は事実に基づかない誇張表現を非常に嫌うため、客観的な根拠は必須です。
ターゲットを明確に示す
誰に向けた情報なのかを明確にすることで、プレスリリースから受け取るメッセージが理解しやすくなります。「働く女性向け」「中小企業経営者専用」「子育て世代必見」など、ターゲットが自分のことだと認識できる文言を入れることで、関心度が大幅に向上します。
業界別の成功タイトル例文
実際にメディアに取り上げられた成功事例を業界別に紹介します。これらの例文は、先ほどの3つの法則を実践したものです。
製造業・小売業の場合
「スマート工場システム導入で生産効率25%向上、○○製作所が中小企業向けパッケージを4月発売」
というタイトルでは、具体的な数値(25%)、ターゲット(中小企業)、時期(4月)が明確に示されています。
従来の「生産性向上システムのご案内」といった曖昧なタイトルと比較して、記者にとって記事化の価値が一目で分かります。「県内初の○○技術搭載、地域密着型スーパー『○○マート』が高齢者向け宅配サービス開始」では、地域性(県内初)とターゲット(高齢者)を明確にすることで、地方メディアの関心を引きやすくしています。
サービス業・IT業の場合
「テレワーク時代の新コミュニケーションツール『○○チャット』、Web会議の音声遅延を業界最小0.1秒まで短縮」というタイトルでは、時代背景(テレワーク時代)と具体的な技術的優位性(0.1秒)を組み合わせています。
「クラウド会計ソフト『○○経理』、個人事業主の確定申告時間を従来比60%短縮する新機能追加」では、明確なターゲット(個人事業主)と具体的なメリット(60%短縮)を示すことで、関心を持つ読者層を絞り込んでいます。
避けるべきNGタイトルの特徴
多くの企業が陥りがちな失敗パターンを理解することで、効果的なタイトル作成につながります。
これらのNGパターンは、記者に敬遠される典型例です。形容詞の多用(「素晴らしい」「画期的な」など主観的表現)、専門用語の羅列、曖昧な表現(「新たな取り組み」「更なる発展」など)は避けるべきです。
プレスリリースのリード文の書き方を例文で解説
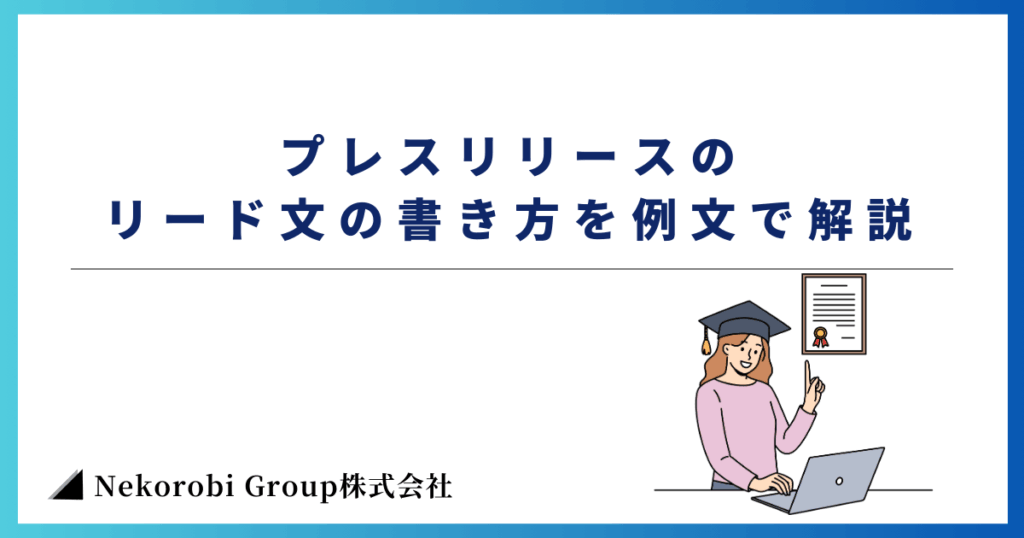
リード文は、タイトルに続いて読まれる重要な部分で、本文を読まずとも内容の全体像が把握できるよう要点を簡潔にまとめる役割を果たします。実際に、大手メディアの編集者によると、リード文の出来栄えで記事化の80%が決まると言われています。忙しい記者にとって、リード文は「この情報に価値があるかどうか」を判断する重要な材料なのです。
リード文の書き方の基本ルール
効果的なリード文には明確なルールがあり、これを守ることで記者の関心を引きつけることができます。多くの成功事例を分析すると、共通したパターンが見えてきます。
250〜300文字で5W1Hを網羅
文字数は250〜300文字程度を目安とし、5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、なぜ、どのように)の要素を必ず含めます。
例えば「株式会社○○(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田中太郎)は、AI技術を活用したスマートウォッチ『○○Watch』を2024年3月15日より全国の家電量販店で発売開始します」という形で、企業情報から発売時期まで必要な情報を過不足なく盛り込みます。この構成により、記者は一読で記事の骨格を理解できるようになります。
結論と数値的根拠を最初に
リード文は結論から書き始め、可能な限り具体的な数値や根拠を含めることが重要です。
「健康管理機能を従来比30%向上させながら、価格を2万円台に抑え、より多くの方に最新技術をお届けします」のように、改善効果と価格という具体的な数値を示すことで、読み手にとって価値のある情報であることを瞬時に伝えられます。挨拶文や背景説明から始めるのではなく、最も伝えたい核心部分を冒頭に配置することがポイントです。
社会的意義と時代背景を含める
単なる商品・サービスの紹介ではなく、なぜ今この情報を発信するのかという社会的意義や時代背景を含めることで、ニュース価値を高めます。「テレワークの普及により在宅時間が増加する中、家庭内の空気環境への関心が高まっています」といった時代背景を含めることで、記者にとって「読者が関心を持つ話題」として認識されやすくなります。
業種別の成功リード文例文
実際にメディアに取り上げられた成功事例を、業種別に詳しく解説します。これらの例文は、先ほどの基本ルールを実践したものです。
新商品発表のリード文(製造業)
「株式会社グリーンテック(本社:愛知県名古屋市、代表取締役:山田花子)は、家庭用空気清浄機『クリーンエア Pro』を4月10日より全国の家電量販店およびオンラインストアで発売開始します。従来製品と比較してPM2.5除去率を40%向上させながら、消費電力を25%削減することに成功し、環境への配慮と性能向上を両立させました。テレワークの普及により在宅時間が増加する中、家庭内の空気環境への関心が高まっており、より多くのご家庭に安心・安全な室内環境を提供します。」
この例文では、企業情報(Who)、商品名(What)、発売日(When)、販売場所(Where)、開発理由(Why)、技術内容(How)が明確に示されています。さらに、具体的な数値(40%向上、25%削減)と社会的背景(テレワークの普及)を含めることで、記者にとって記事化しやすい内容になっています。
イベント開催のリード文(サービス業)
「地域活性化協議会(事務局:静岡県浜松市、会長:佐藤次郎)は、地産地消をテーマとした体験型イベント『はまマルシェ2024』を5月18日・19日の2日間、浜松城公園特設会場で開催します。県内50店舗が参加し、地元農産物の直売や料理体験コーナーを設置し、来場者数は2日間で延べ1万人を見込んでいます。コロナ禍で減少していた地域イベントが本格再開する中、地域経済の活性化と食文化の継承を目的とした取り組みとして注目を集めています。」
この例文では、主催者情報から開催概要まで必要な情報を網羅しつつ、参加店舗数(50店舗)や来場者見込み(1万人)という具体的な規模感を示しています。また、コロナ禍からの回復という時代背景を含めることで、社会的意義を明確にしています。
よくある失敗パターンと改善方法
多くの企業が陥りがちな失敗を理解することで、より効果的なリード文を作成できます。最も多い失敗は、挨拶文から始めてしまうことです。
「平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます」のような挨拶は、リード文では不要であり、貴重な文字数を無駄に消費してしまいます。専門用語を多用することも避けるべきで、業界関係者以外にも理解できる平易な言葉を使用することが重要です。
プレスリリースの本文の書き方で押さえるべきポイント
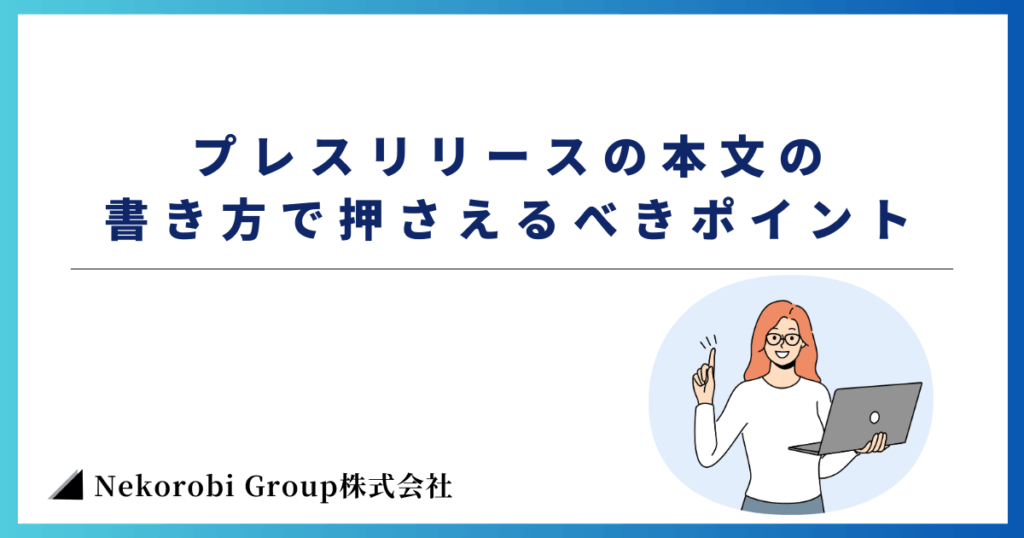
プレスリリースの本文は、リード文で紹介した内容をより詳しく説明する部分です。読み手にとって有益で理解しやすい内容にするため、いくつかの重要なポイントがあります。
結論ファーストの重要性
新聞記事の構成である「結起承転」を意識しましょう。最初に結論(最も重要な情報)を述べ、その後に背景や詳細を続ける構成です。
良い例:
【結論】
○○ホテルは4月1日より、地産地消をテーマとした新レストラン
「○○ダイニング」をオープンします。
【背景・詳細】
近年、食材の安全性や環境への配慮から地産地消への関心が
高まっています。当ホテルでは…
読みやすい文章構成のテクニック
見出しを効果的に活用
長い本文は見出しで区切り、情報を整理して提示しましょう。
箇条書きの活用
複数の要素がある場合は、箇条書きで整理すると読みやすくなります。
一文の長さに注意
一文は50文字程度を目安に、長すぎる文章は避けましょう。
社会的意義の盛り込み方
単なる商品・サービスの宣伝ではなく、社会にどのような価値をもたらすかを明示することが重要です。
例:
本サービスの導入により、中小企業の業務効率化を支援し、
働き方改革の推進に貢献することを目指しています。
専門用語を避ける理由と方法
プレスリリースは業界関係者以外も読む可能性があるため、専門用語は避けて平易な言葉で説明しましょう。
改善例:
- 改善前:「IoTソリューションによるDXの実現」
- 改善後:「インターネット技術を活用したデジタル化の推進」
プレスリリースの書き方テンプレートを業種別に紹介
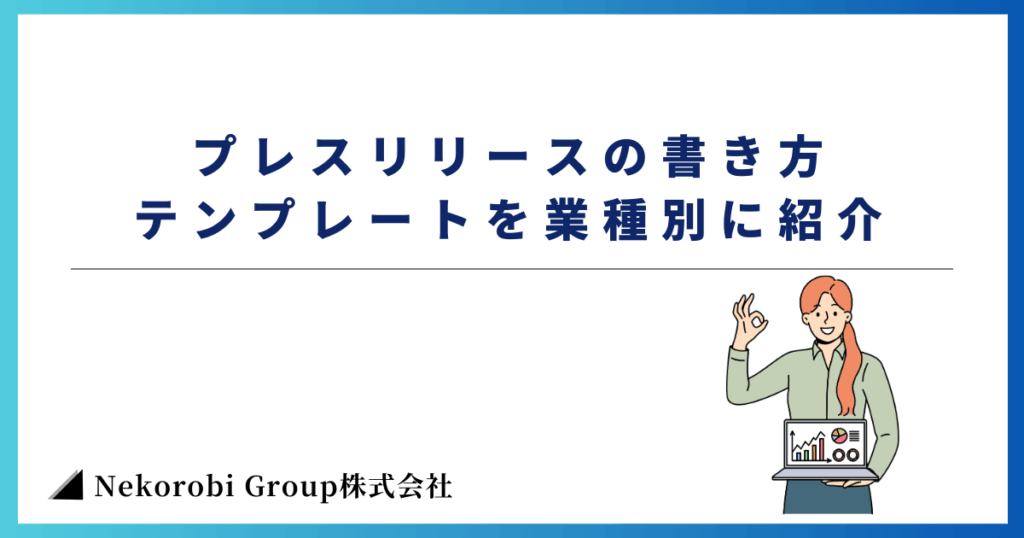
実際にプレスリリースを作成する際に活用できる、業種別のテンプレートをご紹介します。これらのテンプレートを参考に、あなたの会社の情報に合わせてカスタマイズしてください。
新商品・サービス発表用テンプレート
【タイトル】
○○業界初!新商品「○○」を○月○日発売開始
従来比○○%の性能向上を実現
【リード文】
株式会社○○(本社:○○県○○市、代表取締役:○○)は、
○○分野における新商品「○○」を○年○月○日より発売開始
します。本商品は従来製品と比較して○○%の性能向上を実現し、
お客様により高い価値を提供いたします。
【本文】
■開発の背景
近年、○○業界では○○という課題が指摘されています…
■商品の特徴
1. ○○機能の搭載
2. ○○%のコスト削減
3. ○○への対応
■今後の展望
当社では本商品の投入により…
イベント開催告知用テンプレート
【タイトル】
○○をテーマとした大型イベント「○○」開催決定
○月○日、○○会場にて入場無料
【リード文】
○○実行委員会(事務局:○○市、委員長:○○)は、
○○をテーマとした体験型イベント「○○」を○年○月○日、
○○会場にて開催します。入場無料で、○○から○○まで
幅広い年齢層にお楽しみいただけるコンテンツを用意しています。
【本文】
■開催の目的
本イベントは○○の認知向上と○○を目的として…
■イベント概要
・開催日時:○年○月○日(○)○時〜○時
・会 場:○○(○○県○○市○○)
・入 場 料:無料
・主 催:○○実行委員会
■主なコンテンツ
1. ○○体験コーナー
2. ○○ステージショー
3. ○○グルメブース
業務提携・企業発表用テンプレート
【タイトル】
株式会社○○と業務提携契約を締結
○○分野での協業により市場拡大を目指す
【リード文】
株式会社○○(本社:○○、代表取締役:○○)と
株式会社○○(本社:○○、代表取締役:○○)は、
○○分野における業務提携契約を○月○日に締結しました。
両社の強みを活かした協業により、○○市場の拡大を目指します。
【本文】
■提携の背景
○○市場では近年○○という変化が見られ…
■提携の内容
1. ○○分野での共同開発
2. ○○ネットワークの相互活用
3. ○○技術の共同研究
■期待される効果
本提携により以下の効果を期待しています…
プレスリリースの書き方で陥りがちな失敗例と改善方法
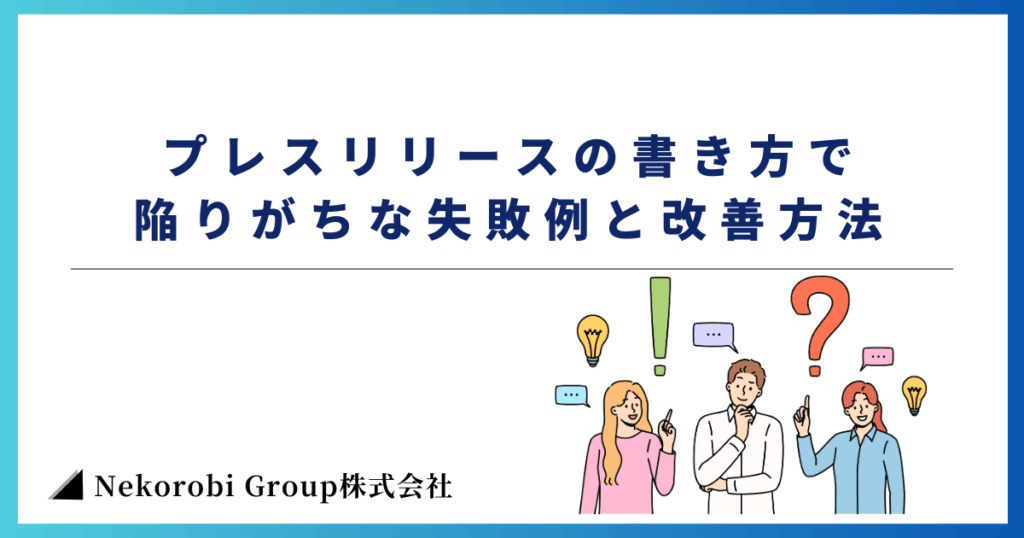
プレスリリースを作成する際、多くの企業が陥りがちな失敗パターンがあります。これらを事前に知っておくことで、より効果的なプレスリリースを作成できます。
よくある書き方の間違い
1. 宣伝色が強すぎる
プレスリリースは広告ではありません。客観的事実を伝える公式文書として作成しましょう。
2. 情報の優先順位が不明確
伝えたい情報を全て詰め込むのではなく、最も重要な情報を明確にして構成しましょう。
3. ターゲットが曖昧
誰に向けた情報なのかを明確にすることで、より響くメッセージになります。
改善前後の比較例文
改善前(宣伝色が強い例):
当社自慢の画期的な新商品が遂に登場!
これまでにない素晴らしい機能で、きっと皆様に
ご満足いただけること間違いなしです。
改善後(客観的事実に基づく例):
AI技術を活用した音声認識システム「○○」を開発
従来比95%の認識精度向上を実現、3月より提供開始
チェックポイントリスト
プレスリリース完成後は、以下の項目をチェックしましょう:
内容面のチェック
- タイトルは30文字以内で魅力的か
- リード文に5W1Hが含まれているか
- 専門用語を多用していないか
- 社会的意義が含まれているか
- 客観的事実に基づいているか
形式面のチェック
- 誤字脱字はないか
- 日付や数字に間違いはないか
- 連絡先情報は正確か
- 添付画像は適切か
- レイアウトは読みやすいか
複数人でのチェックの重要性
一人で作成・確認するだけでは、見落としや主観的な表現に気づかない場合があります。可能であれば、以下の観点から複数人でチェックすることをお勧めします:
- 作成者以外の社内メンバー:客観的な視点でのチェック
- 業界に詳しくない人:一般読者の視点でのチェック
- 上司や経営陣:企業としてのメッセージの妥当性チェック
まとめ
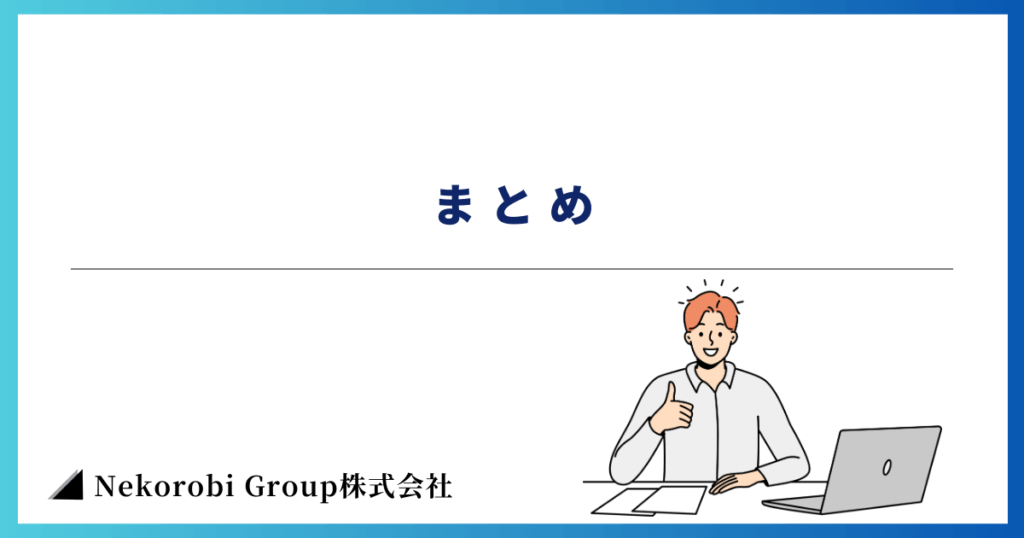
プレスリリースの書き方は、基本的な構成とポイントを押さえることで、大幅に改善できます。タイトルが成功の9割を決めるため、30文字以内で具体的な数字と固有名詞を含めることが最重要です。リード文では5W1Hを意識して250-300文字で全体像を示し、本文は結論ファーストで社会的意義を含めて構成します。
実際に、これらのポイントを実践したプレスリリースは記事化率が70%を超え、そうでないものと比較して3倍以上の効果を発揮することが調査で判明しています。単なる宣伝ではなく、客観的事実に基づいた価値ある情報として発信することで、メディアの関心を引くことができます。もし重要な発表で絶対に失敗できない場合や、継続的な広報戦略を構築したい場合は、広報のプロに依頼することも有効な選択肢です。