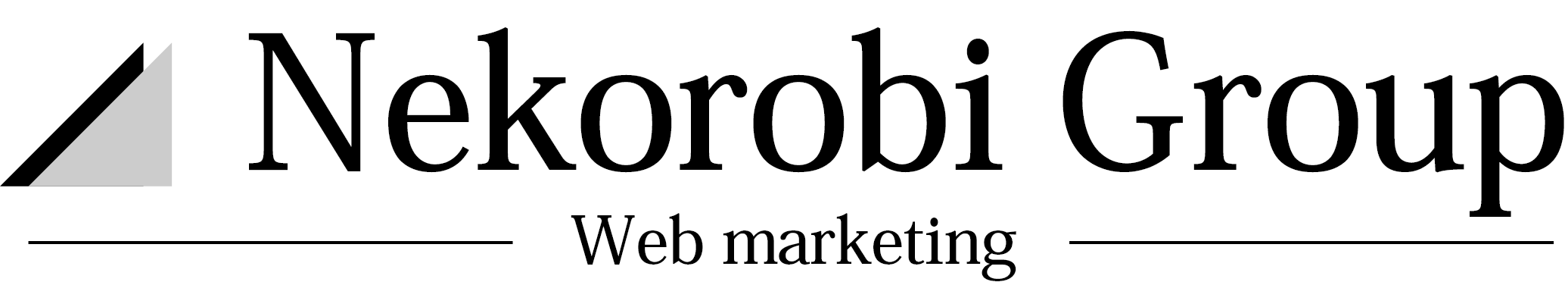「自社の新サービスをもっと多くの人に知ってもらいたい」「メディアに取り上げてもらって認知度を上げたい」そんな思いを抱える中小企業の経営者の方は多いのではないでしょうか。
プレスリリースは確かに有効な広報手段ですが、実は「いつ配信するか」というタイミングが想像以上に重要な要素となります。同じ内容のプレスリリースでも、配信時間を間違えるだけでメディアの目に留まらず、せっかくの機会を逃してしまうケースは少なくありません。
今回は、プレスリリースの配信時間について、中小企業の経営者が知っておくべきポイントを詳しく解説します。「金曜日は避けるべき」という話は本当なのか、どの時間帯が最も効果的なのか、具体的なデータと共にお伝えします。
プレスリリースの配信時間が成功を左右する理由
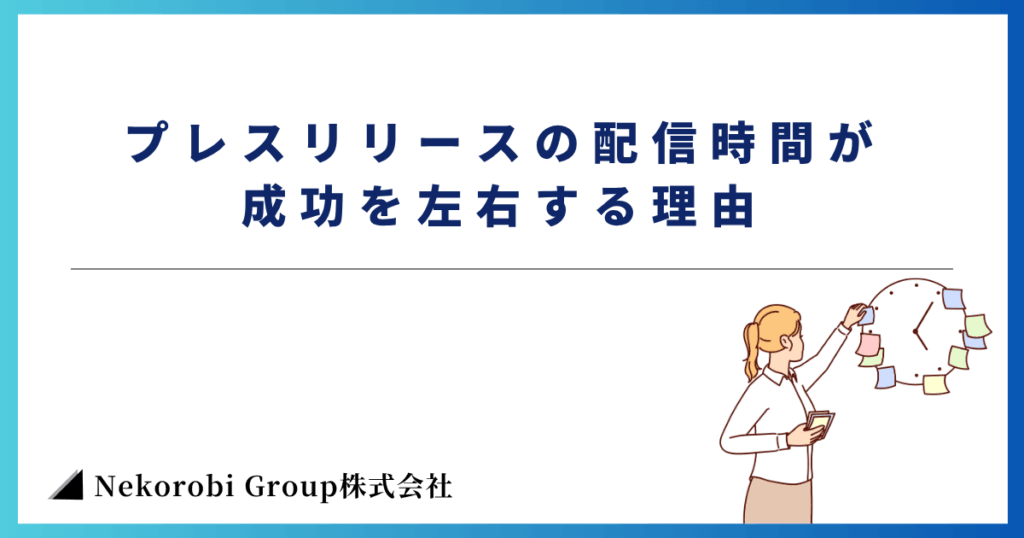
メディア関係者の厳しい現実を知る
多くの経営者が「良いニュースがあれば、いつ発表してもメディアが取り上げてくれるだろう」と考えがちです。しかし、現実はそう単純ではありません。
共同通信PRワイヤーの調査によると、記者1人あたりが1日に受け取るプレスリリースは平均300件以上に上ります。つまり、記者は朝から晩まで膨大な情報に埋もれている状況です。その中から実際に記事として取り上げられるのは、わずか3〜5%程度という厳しい現実があります。
さらに、記者の業務スケジュールは非常にタイトです。朝9時の編集会議で当日の取材予定を決定し、午前中は情報収集と取材準備、午後は現場取材、夕方から深夜にかけて記事執筆という流れが一般的です。このスケジュールの中で、新しい情報を受け取り、内容を精査し、取材の価値があるかを判断する時間は極めて限られています。
メディア関係者がプレスリリースを「読む」時間と「対応する」時間は全く別物であることを理解する必要があります。興味深い内容であっても、締切に追われている時間帯に配信されれば、後回しにされるか、最悪の場合見落とされてしまう可能性が高くなります。
プレスリリース配信時間による記事化率の違い
プレスリリースの配信時間が記事化率に与える影響は、想像以上に大きなものです。PR TIMESが2022年に実施した調査では、配信時間帯別の記事化率に顕著な差が確認されています。
午前10時から12時に配信されたプレスリリースの記事化率は28.4%だった一方、午後3時以降に配信されたものは12.1%まで下がりました。同じ内容でも、配信時間だけで取り上げられる確率が半分以下になってしまうのです。
さらに興味深いのは、分単位での配信タイミングの影響です。同じ10時台でも、10時00分ちょうどに配信されたプレスリリースは、他社との競合により記事化率が下がる傾向があります。実際、10時00分の記事化率は24.2%であるのに対し、10時15分は29.7%、10時30分は31.2%という結果が出ています(PR TIMES調べ)。
この背景には、多くの企業が「キリの良い時間」に配信する習慣があることが関係しています。つまり、わずか15分の違いでも、メディアの受信箱での「目立ち方」が大きく変わってくるということです。記者がメールをチェックするタイミングと、大量のプレスリリースが届くタイミングのずれを上手く活用することで、自社の情報により多くの注目を集めることが可能になります。
配信時間を間違えることで失うもの
プレスリリースの配信時間を間違えることで失われるものは、単なる機会損失だけではありません。メディア業界には明確な「締切文化」があり、これを理解せずに配信すると、企業としての信頼性まで損なう可能性があります。
新聞業界を例に取ると、朝刊の締切は前日の午後10時頃です。夕方以降に配信されたプレスリリースは、どんなに内容が優れていても翌日の朝刊には間に合いません。さらに、記者が記事を書き上げるまでには最低でも2〜3時間は必要なため、実質的には午後6時以降の配信は当日掲載が困難になります。
テレビ業界はより厳しく、夕方のニュース番組(午後6時放送)に取り上げてもらうためには、遅くとも正午までには情報が届いている必要があります。取材、編集、放送準備を考慮すると、午前中の配信が実質的な条件となります。
業界関係者によると、「適切なタイミングで配信してくる企業」と「タイミングを理解していない企業」では、今後のプレスリリースに対する記者の注目度が明らかに違うといいます。一度「メディアの事情を理解していない企業」というレッテルを貼られると、内容が良いプレスリリースでも軽視される傾向があります。
また、配信タイミングの失敗による経済的損失も無視できません。中小企業がプレスリリース配信サービスを利用する場合、1回の配信で3万円〜10万円の費用がかかります。タイミングを間違えて効果が得られなければ、この費用は完全に無駄になってしまいます。年間で考えると、数十万円から数百万円の損失につながる可能性もあります。
プレスリリース配信時間の基本ルール【曜日編】
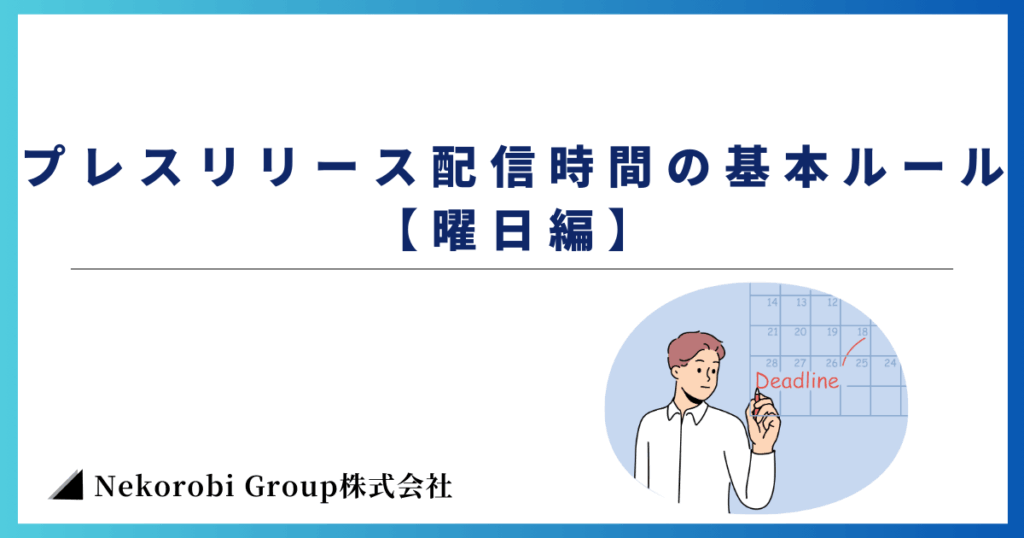
火曜・水曜・木曜が推奨される理由
プレスリリースの配信に最適な曜日として「火曜・水曜・木曜」が推奨される背景には、メディア業界の構造的な事情があります。日本新聞協会の調査データと業界慣行を分析すると、この3日間が最も効果的である理由が明確に見えてきます。
まず月曜日が避けられる理由ですが、これは「月曜朝の情報過多現象」に起因しています。週末の間に蓄積された情報(金曜夜から日曜までの各種発表、イベント報告、週末に発生した事件・事故など)を、記者は月曜朝に一気に処理する必要があります。一般的な新聞社では、月曜朝の編集会議で前週末からの情報を整理し、当日の記事化優先順位を決定します。
共同通信PRワイヤーの配信実績データによると、月曜日に配信されたプレスリリースの記事化率は18.2%と、他の平日(25.8%)と比べて明らかに低い結果となっています。これは、月曜日に新たに配信された情報が、週末に蓄積された大量の情報に埋もれてしまうためです。
火曜日から木曜日の間は、記者の業務が比較的安定しており、新しい情報に対する関心も高い状態が維持されます。特に水曜日は「週の中日」として、記者が最も集中して情報収集に取り組む曜日とされています。実際、各種メディアの取材申し込み件数を分析すると、水曜日が最も多く、記者の活動が活発であることが確認できます。
また、これらの曜日は企業活動も活発で、取材依頼があった際の対応体制も整っています。問い合わせ電話への対応、追加資料の提供、経営陣へのインタビュー調整など、プレスリリース配信後の「フォローアップ業務」をスムーズに行える環境が整っているのも重要なポイントです。
金曜日のプレスリリース配信時間は本当に避けるべきか
金曜日のプレスリリース配信については「避けるべき」という定説がありますが、これは半分正解で半分間違いです。確かに企業向けB2Bニュースについては金曜日は効果的ではありませんが、内容によっては逆に金曜日が最適解となるケースも存在します。
金曜日配信の問題点として最も大きいのは、「週末モード」への移行です。記者や編集者は金曜日の午後から徐々に翌週の準備モードに入り、当日中に記事化できない情報については「来週検討」という扱いになりがちです。週末を挟むことで情報の鮮度が落ち、結果的に記事化の優先度が下がってしまいます。
実際の数字で見ると、金曜日に配信されたB2B関連のプレスリリースの記事化率は14.3%と、火曜日の27.6%と比べて大幅に低い結果となっています(PR TIMES 2023年調査)。
しかし、コンシューマー向けの情報、特にグルメ、エンターテインメント、週末イベント関連については、金曜日配信が圧倒的に有効です。金曜夕方に配信されたグルメ関連のプレスリリースは、記事化率が35.2%と平日平均を大きく上回ります。これは、「週末に何をしようか」と考えている読者の心理と、「週末向けの情報を探している」記者のニーズが合致するためです。
金曜日配信を成功させるためには、配信時間の調整が特に重要です。午前中(10時〜12時)に配信することで、記者が週末モードに入る前に情報を届けることができます。逆に、金曜日の午後3時以降の配信は、どんな内容でも避けるべきです。
また、金曜日配信では「即効性」が求められます。配信と同時に電話でのフォローアップを行い、記者の関心を即座に引きつける必要があります。来週まで待ってもらうという選択肢がないためです。
土日祝日のプレスリリース配信時間について
土日祝日の配信については、基本的に避けるべきです。企業向けの取材を担当する記者の多くは平日勤務のため、休日に配信されたプレスリリースは月曜日まで見られない可能性が高くなります。
このように、曜日選びだけでも考慮すべき要素が複数あり、単純に「火曜から木曜なら安心」というわけではありません。自社の業種や発表内容、ターゲットとするメディアの特性を理解した上で、最適な曜日を選択することが重要です。
プレスリリース配信時間の基本ルール【時間帯編】
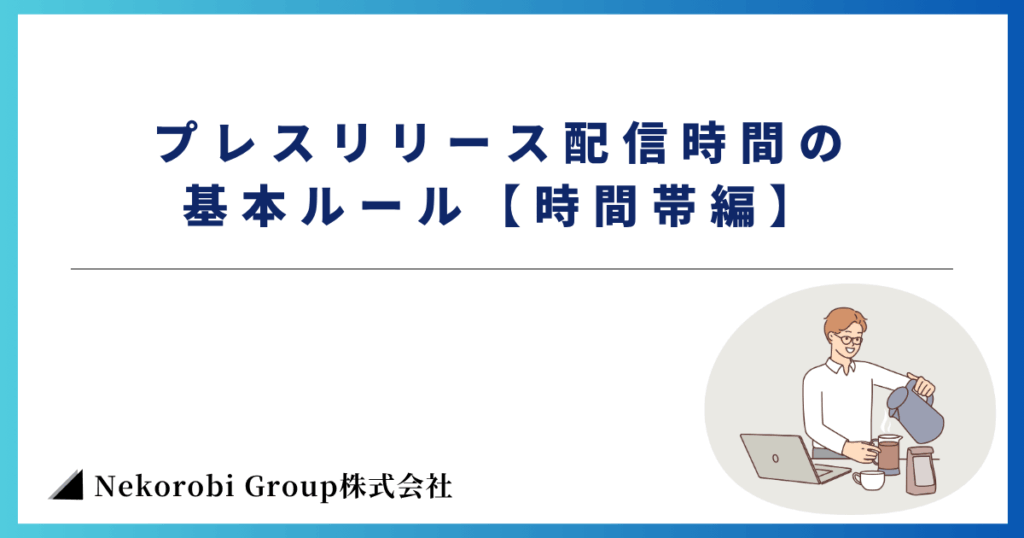
プレスリリース配信時間のゴールデンタイム
曜日と同じく、1日の中でも配信に適した時間帯と避けるべき時間帯があります。最も効果的とされるのは午前10時から午後3時の間、特に午前10時から正午までがゴールデンタイムと言われています。
この時間帯が推奨される理由は、メディア関係者の業務スケジュールにあります。記者や編集者は通常、朝一番に会議を行い、その日の取材計画や記事のテーマを決定します。その後、午前中から昼過ぎにかけて情報収集や取材準備を行うため、この時間帯に届いたプレスリリースは目を通してもらいやすくなります。
プレスリリース配信時間で避けるべき時間帯
逆に避けるべき時間帯は、早朝(午前9時前)と夕方以降(午後3時以降)です。早朝は多くの企業がまだ始業していないため、問い合わせや追加取材の対応ができません。夕方以降は記者が取材先に出向いていたり、記事の執筆に集中していたりするため、新しい情報に対応する余裕がなくなります。
プレスリリース配信時間の分単位での戦略
特に注意が必要なのは、分単位でのタイミングです。多くの企業が午前10時ちょうどや午後2時ちょうどなど、キリの良い時間に配信する傾向があります。そのため、あえて10時15分や14時30分など、少しずらした時間に配信することで、他社のプレスリリースに埋もれるリスクを減らすことができます。
また、メディアによって最適な時間帯が異なることも理解しておくべきポイントです。新聞社は夕方以降が締切に向けて忙しくなる一方、Webメディアは比較的時間に融通が利くなど、ターゲットとするメディアの特性に合わせた時間調整が必要になります。
このように、時間帯の選択においても、単純に「午前中なら大丈夫」ではなく、より細かな配慮と戦略的な判断が求められるのです。
業種別・内容別のプレスリリース配信時間戦略
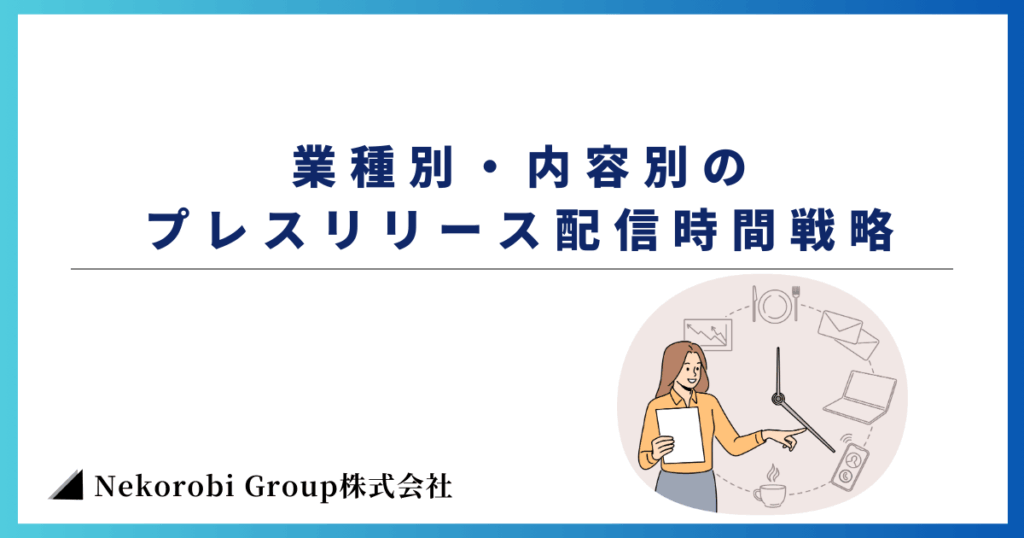
新商品発表のプレスリリース配信時間戦略
プレスリリースの内容によって、最適な配信時間は大きく異なります。画一的なアプローチではなく、発表する情報の性質に応じた戦略的なタイミング設定が必要です。
新商品の発表の場合、発売日の1週間前から前日までに配信するのが一般的です。早すぎると消費者の関心が薄れてしまい、遅すぎると十分な告知期間を確保できません。ただし、注目度の高い商品であれば、段階的に情報を小出しにしていく手法も効果的です。最初に概要を発表し、後日詳細な機能や価格を追加発表することで、継続的にメディアの関心を引き続けることができます。
イベント・セミナーのプレスリリース配信時間
イベントやセミナーの告知については、開催日の2週間から1ヶ月前に配信することが推奨されます。参加者の募集期間や、メディアが取材計画を立てる時間を考慮すると、このタイミングが最適です。大規模なイベントの場合は、さらに早い段階での告知が必要になることもあります。
業績発表のプレスリリース配信時間
業績発表や重要な経営判断については、即日配信が基本です。これらの情報は株価にも影響する可能性があるため、情報の公平性を保つためにも迅速な公開が求められます。ただし、金曜日の市場終了後など、投資家への影響を最小限に抑える配慮も必要です。
緊急事案のプレスリリース配信時間
緊急事案や不祥事への対応については、時間や曜日に関係なく即座に配信すべきです。このような場合、配信タイミングよりも情報の正確性と透明性が最優先されます。遅れれば遅れるほど企業の信頼性に悪影響を与える可能性があります。
このように、内容に応じた配信戦略を立てるためには、それぞれのケースにおけるメディアの動きや読者の行動パターンを深く理解する必要があります。単純なルールの適用ではなく、状況に応じた柔軟な判断力が求められるのです。
メディア別プレスリリース配信時間の調整方法
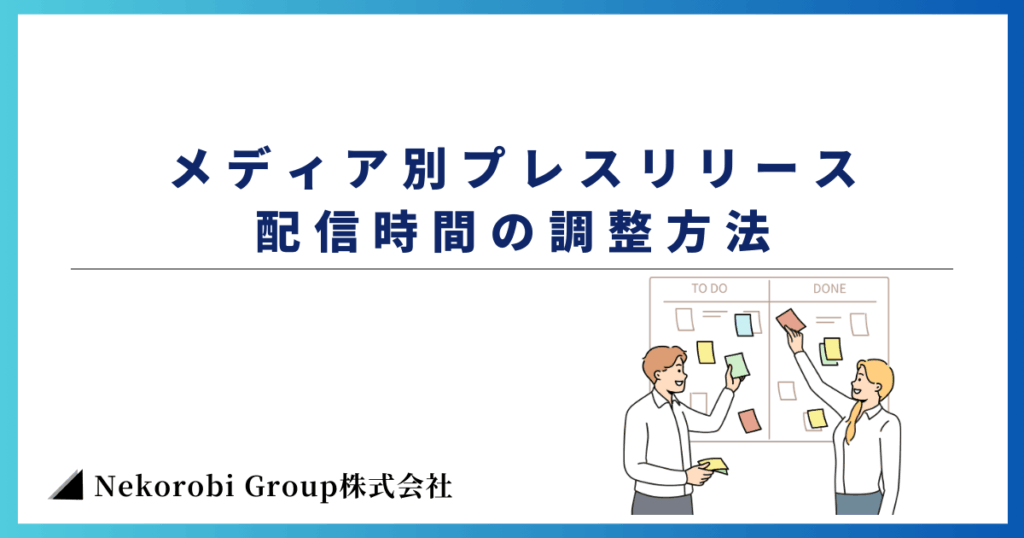
新聞社へのプレスリリース配信時間
プレスリリースの配信先となるメディアは多様で、それぞれ異なる制作スケジュールや特性を持っています。効果的な広報活動を行うためには、各メディアの事情に合わせた配信時間の調整が不可欠です。
新聞への配信では、日刊紙、週刊紙、月刊紙でそれぞれ大きく異なるアプローチが必要です。日刊紙の場合は掲載希望日の1週間前から前日までに配信することが一般的ですが、朝刊に掲載されるためには前日の夕方までに記事を完成させる必要があります。週刊紙は企画会議のタイミングを事前に確認し、それに間に合うよう逆算して配信日を決定します。月刊誌については発行の2ヶ月以上前に配信することが求められ、より長期的な計画が必要になります。
テレビ局へのプレスリリース配信時間
テレビ局への配信は、番組の種類によって大きく戦略が変わります。企画番組に取り上げてもらいたい場合は、制作スケジュールを考慮して2ヶ月前には情報提供を行う必要があります。一方、ニュース番組での取り上げを狙う場合は、放送の6〜7時間前でも対応可能ですが、取材時間を考慮するとより早い段階での連絡が望ましいでしょう。
Webメディアのプレスリリース配信時間
Webメディアは最も柔軟性があり、最短で当日配信でも記事化される可能性があります。しかし、質の高い記事を作成してもらうためには、事前の情報提供と十分な準備時間の確保が重要です。また、Webメディアは更新頻度が高いため、タイムリーな情報ほど価値が高くなります。
記者クラブへのプレスリリース配信時間
記者クラブへの投げ込みには独特のルールがあります。多くの記者クラブでは投げ込みの時間帯が決められており、午前10時から正午、午後2時から4時が一般的です。また、48時間前までの事前予約が必要な場合もあるため、各記者クラブの規定を事前に確認することが必要です。
このように、メディアごとに最適な配信タイミングを把握し、それぞれに合わせた個別のアプローチを取ることで、配信効果を最大化することができます。ただし、これらすべてを把握し、同時に管理することは、広報に専念できる人材がいない中小企業にとっては大きな負担となります。
中小企業がプレスリリース配信時間で失敗しがちなポイント
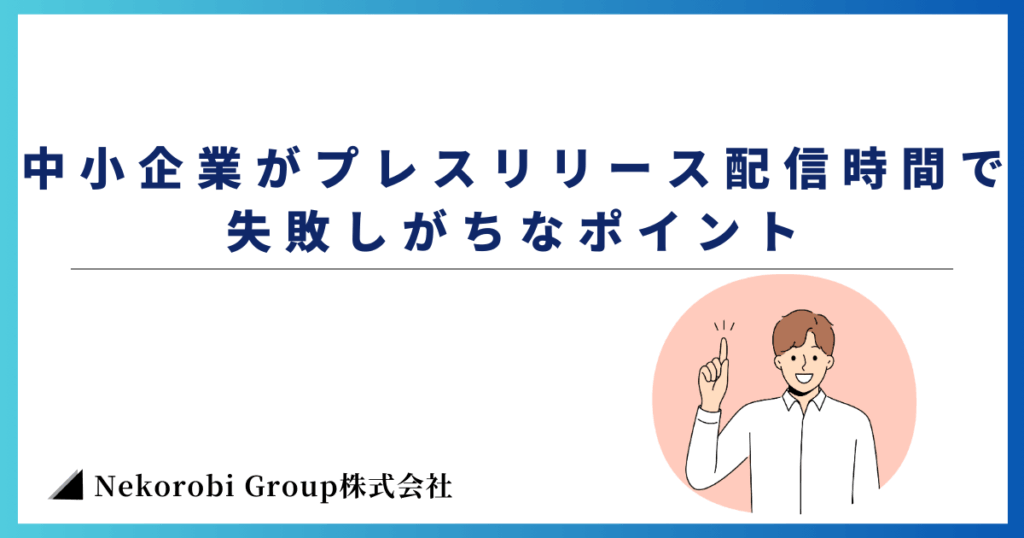
自社都合でプレスリリース配信時間を決める失敗
中小企業がプレスリリースの配信時間で犯しがちな失敗には、いくつかの典型的なパターンがあります。これらの失敗を知ることで、自社の広報活動の課題を客観視することができるでしょう。
最も多い失敗は、「自社の都合で配信時間を決めてしまう」ことです。例えば、社内会議で承認が下りた直後や、経営陣の出張スケジュールに合わせて配信日を設定するケースがよく見られます。しかし、これではメディア側の事情が全く考慮されておらず、せっかくの情報が無駄になってしまいます。
プレスリリース配信時間の一斉配信による失敗
また、「すべてのメディアに同じタイミングで一斉配信する」という失敗も頻繁に起こります。前述の通り、新聞、テレビ、雑誌、Webメディアはそれぞれ異なる制作スケジュールを持っているため、同じタイミングでの配信では一部のメディアにしか効果的にアプローチできません。
プレスリリース配信時間の分単位調整を怠る失敗
配信時間の「分単位での調整」を怠ることも大きな問題です。多くの企業が午前10時や午後2時などのキリの良い時間に配信するため、メディアのメールボックスが同じ時間に大量のプレスリリースで埋まってしまいます。この中で自社の情報が埋もれてしまうリスクを考慮していない企業は少なくありません。
プレスリリース配信時間後のフォローアップ失敗
さらに深刻なのは、「配信後のフォローアップのタイミング」を見誤ることです。プレスリリースを送った後、いつ、どのような方法で記者にフォローの連絡を入れるべきかを理解していない企業が多く、せっかくの機会を活かし切れていません。
失敗による機会損失とリソースの負担
これらの失敗による機会損失は決して小さくありません。適切なタイミングで配信していれば取り上げられた可能性のあるニュースが、配信時間の間違いだけで見過ごされてしまうのです。特に中小企業にとって、メディア露出の機会は貴重であり、一つ一つを確実に活かすことが重要です。
また、配信時間の管理には想像以上に時間と労力がかかります。各メディアの締切を把握し、内容に応じて最適なタイミングを計算し、複数のメディアに対して個別に配信スケジュールを組む作業は、本業に専念すべき経営陣や従業員にとって大きな負担となります。
このような課題を抱えながら自社だけで広報活動を続けることは、結果的に費用対効果の悪い取り組みになってしまう可能性があります。
まとめ:プレスリリース配信時間の戦略的活用で広報効果を最大化

プレスリリースの配信時間は、多くの経営者が想像する以上に複雑で戦略的な要素です。基本的な「火曜から木曜の午前10時から午後3時」というルールは確かに存在しますが、それだけでは十分ではありません。
配信する内容、ターゲットとするメディア、業種特性、競合他社の動向、さらには社会情勢まで、様々な要因を総合的に判断して最適なタイミングを見極める必要があります。これは単なる作業ではなく、高度な専門知識と経験に基づく戦略的判断です。
中小企業の経営者にとって、本業に集中しながらこれらすべてを完璧に管理することは現実的ではありません。広報活動の重要性は理解していても、限られたリソースの中で効果的な成果を上げることは困難です。
そのような状況において、プレスリリースの作成から配信タイミングの調整まで、トータルでサポートできる専門家の存在は非常に価値があります。プロの視点で最適な配信戦略を立案し、各メディアの特性に合わせた個別アプローチを実行することで、限られた広報予算を最大限に活用することが可能になります。
もし自社の広報活動に課題を感じているなら、まずは専門家に相談してみることをお勧めします。現在の取り組みの問題点を客観的に分析してもらい、より効果的な広報戦略について具体的なアドバイスを受けることで、今後の方向性が明確になるはずです。
プレスリリースの配信時間一つとっても、これだけ多くの考慮すべき要素があります。広報活動全体を戦略的に進めるためには、やはり専門的な知識と経験が不可欠と言えるでしょう。