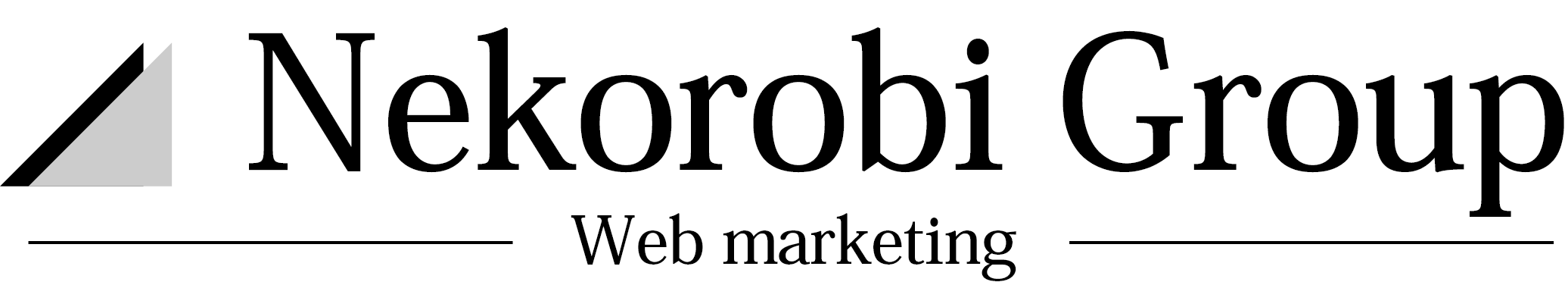「うちの会社も広報でSNS担当を置いた方がいいと聞くけれど、実際に何をやってもらえばいいのか分からない」「SNS担当者を採用したいが、どんな業務を任せるべきか具体的にイメージできない」このような悩みを抱える中小企業の経営者は少なくありません。
現代のマーケティング戦略において、SNSを活用した情報発信は企業の認知度向上や顧客エンゲージメント強化に欠かせない要素となっています。広報におけるSNS担当者は、単なる投稿作業者ではなく、企業ブランディングの最前線で活躍する重要なポジションです。
この記事では、SNS担当者の具体的な業務内容から必要なスキル、各プラットフォームでの運用戦略、さらには内製と外注の判断基準まで、経営者が知っておくべき知識を体系的に解説します。
広報におけるSNS担当とは?基本的な役割を理解しよう

SNS担当の定義と企業における位置づけ
広報のSNS担当者は、企業の公式SNSアカウントを通じて情報発信を行う専門職です。従来の広報活動がメディアへのプレスリリース配信や記者との関係構築を中心としていたのに対し、SNS担当者は消費者と直接コミュニケーションを図る役割を担います。この職種は「中の人」とも呼ばれ、企業の顔として親しみやすさと専門性を両立させることが求められます。
現代のビジネス環境において、SNS担当者は企業の情報発信戦略の要となっています。消費者の情報収集行動がデジタル化する中、企業メッセージを効果的に届けるためには、各SNSプラットフォームの特性を理解し、適切なコンテンツを継続的に発信する必要があります。また、従来のマスメディアを通じた一方向的な情報発信とは異なり、SNSでは双方向のコミュニケーションが前提となるため、リアルタイムでの対応力も重要な要素となります。
SNS担当が企業にもたらす価値
広報のSNS担当者が企業にもたらす価値は多岐にわたります。まず、費用対効果の高いマーケティング活動を実現できる点が挙げられます。テレビCMや新聞広告と比較すると、SNS運用にかかるコストは格段に低く、中小企業でも継続的な情報発信が可能です。また、投稿に対する反応やエンゲージメント率といった具体的な数値で効果測定ができるため、ROIを明確に把握できます。
さらに、SNS担当者は企業のブランドイメージ向上に直接的に貢献します。適切な情報発信により企業の専門性や信頼性を伝えることで、潜在顧客の認知度向上や既存顧客のロイヤリティ強化が期待できます。特に重要なのは、顧客との直接的な接点を持てることです。商品やサービスに関する質問への迅速な回答、クレーム対応、新商品情報の発信など、顧客満足度の向上に直結する活動を行えます。
広報のSNS担当が行う具体的な業務内容
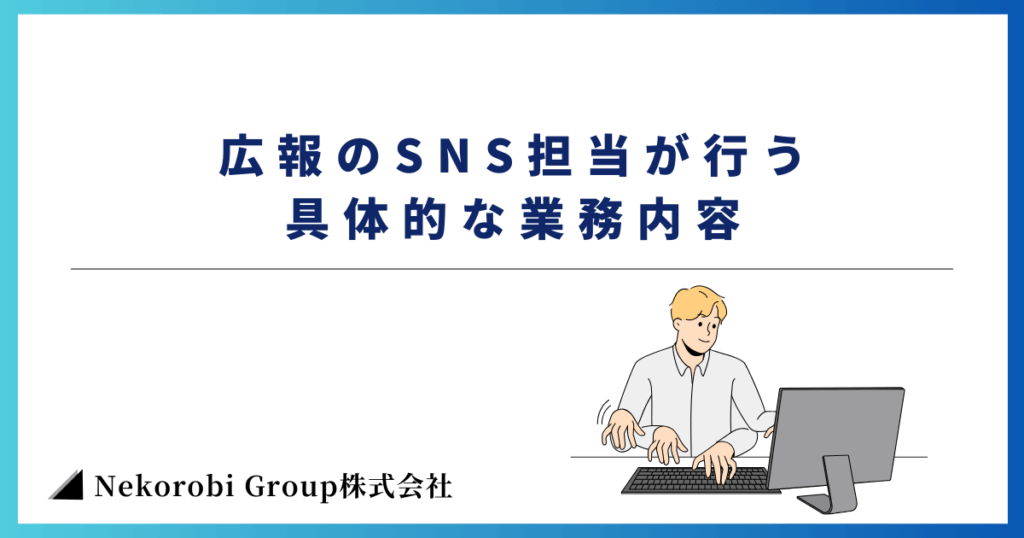
戦略立案から投稿までの一連の流れ
広報のSNS担当者の業務は、まず年間および月間の戦略立案から始まります。企業の経営方針やマーケティング目標に基づき、SNSでの情報発信方針を決定します。この段階では、ターゲットとなる顧客層の明確化、各SNSプラットフォームの役割分担、投稿頻度や内容の大枠を設定します。具体的には、新商品の発表時期に合わせたキャンペーン計画や、季節イベントに連動した企画などを年間スケジュールに組み込みます。
日々の業務では、投稿コンテンツの企画・制作が中心となります。文章作成、画像や動画の編集、ハッシュタグの選定など、一つの投稿を完成させるまでに複数の工程があります。投稿のスケジューリングには専用ツールを活用し、最適な投稿時間に自動配信される仕組みを構築します。また、複数のプラットフォームを運用する場合は、それぞれの特性に合わせてコンテンツをアレンジする必要があります。品質管理の観点から、投稿前の最終チェックも重要な業務の一部です。
ユーザーとのコミュニケーション業務
SNS運用において最も重要な業務の一つが、ユーザーとの双方向コミュニケーションです。投稿に対するコメントへの返信、ダイレクトメッセージでの問い合わせ対応、メンション通知への反応など、リアルタイムでの対応が求められます。これらの対応は単なる事務作業ではなく、企業の顔として適切なトーンでコミュニケーションを行う必要があります。特に商品に関する技術的な質問や購入前の相談については、正確な情報提供が不可欠です。
クレーム対応や炎上リスクの管理も重要な業務です。否定的なコメントや批判的な意見に対しては、冷静かつ建設的な対応を心がけます。問題が拡大する前に適切な対応を行うことで、企業の信頼性を維持できます。また、ポジティブなコメントやユーザー生成コンテンツ(UGC)に対しては、感謝の気持ちを表現し、コミュニティの活性化を図ります。これらの積み重ねが、長期的なブランドロイヤリティの構築につながります。
効果測定と改善業務
広報のSNS担当者は、投稿の効果を定量的に測定し、継続的な改善を行う責任があります。各SNSプラットフォームが提供する分析ツールを活用し、リーチ数、インプレッション数、エンゲージメント率、クリック率などの主要指標を定期的にモニタリングします。これらのデータから投稿の傾向を分析し、どのようなコンテンツがターゲット層に響くかを把握します。
月次および四半期での効果報告書の作成も重要な業務です。経営層や関連部署に対して、SNS活動の成果を数値とともに報告し、今後の戦略提案を行います。ROIの算出、競合他社との比較分析、フォロワーの属性分析なども含めた包括的なレポートを作成します。これらの分析結果を基に、コンテンツ戦略の調整や新しい施策の提案を行い、PDCAサイクルを回していきます。データに基づいた改善提案は、経営層の理解を得やすく、予算確保にも有効です。
広報でSNS担当に求められるスキルと資質
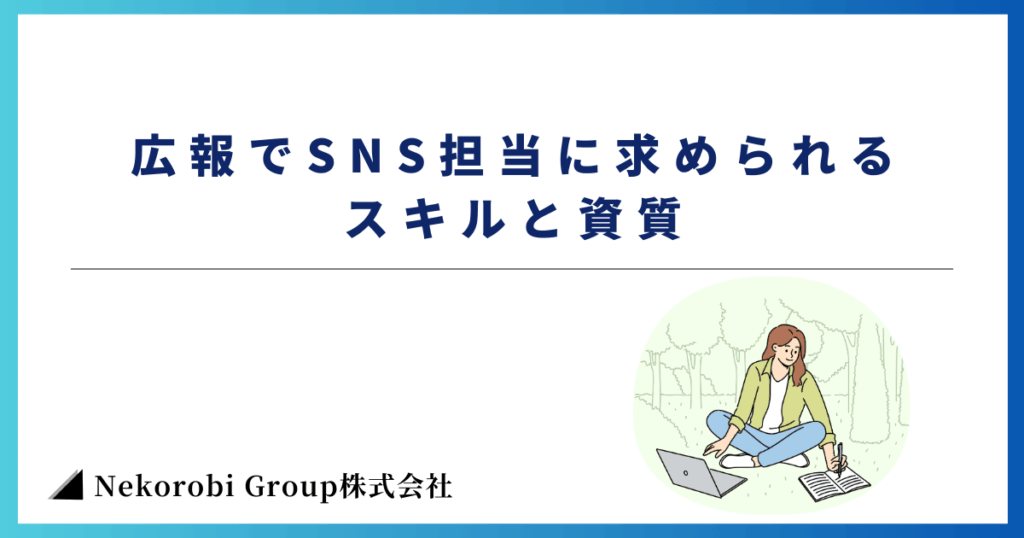
必須となる基本スキル
広報のSNS担当者には、まず優れた文章作成能力が求められます。限られた文字数の中で企業メッセージを効果的に伝える技術、ターゲット層に響く表現力、そして各SNSプラットフォームの特性に合わせた文体の使い分けが必要です。また、視覚的コンテンツの制作スキルも重要で、基本的な画像編集や簡単な動画制作ができることが望ましいです。デザインの知識がなくても、無料ツールを活用して魅力的なビジュアルを作成できる技術は必須といえます。
データ分析能力も現代のSNS担当者に欠かせないスキルです。各種分析ツールから得られる数値を正しく解釈し、改善点を見つけ出す力が求められます。また、これらの分析結果を経営層や他部署にわかりやすく説明するプレゼンテーション能力も重要です。さらに、常に変化するSNSのトレンドやアルゴリズムの変更に対応するため、継続的な学習意欲と情報収集能力が必要です。新しい機能の活用方法を素早く習得し、企業の情報発信に活かす柔軟性も求められます。
成功するSNS担当の特徴
優秀な広報のSNS担当者に共通する特徴として、まず高いコミュニケーション能力が挙げられます。文字だけのやり取りでも相手の感情を理解し、適切な反応ができる共感力が重要です。また、企業の代表として発信を行うため、個人の感情と企業の立場を明確に分離して考える能力が必要です。時には批判的なコメントに対しても冷静に対応し、建設的な対話を心がける精神的な強さも求められます。
計画性と継続力も成功するSNS担当者の重要な特徴です。短期的な成果に一喜一憂するのではなく、長期的な視点でブランド構築を行う忍耐力が必要です。また、日々の投稿を継続するためのスケジュール管理能力や、複数のタスクを効率的に処理する組織力も重要です。さらに、常にユーザーの立場に立って考える顧客志向の思考も欠かせません。企業の都合だけでなく、フォロワーにとって価値のある情報を提供し続ける姿勢が、長期的な成功につながります。
身につけておくと有利な技術
広報のSNS担当者のスキルアップにつながる技術として、まず各種制作ツールの習得が挙げられます。Canva、Adobe Creative Suite、動画編集ソフトなどを使いこなせることで、外部に依頼することなく質の高いコンテンツを制作できます。また、SNS管理ツールやスケジューリングツールの活用により、業務効率を大幅に向上させることができます。HootsuitやBufferなどのプラットフォームを使いこなすことで、複数のSNSアカウントを一元管理できます。
デジタルマーケティング全般の知識も有用です。SEOの基礎知識、Google Analyticsの活用方法、広告運用の基本などを理解していることで、SNS活動を他のマーケティング施策と連携させることができます。また、コミュニティマネジメントの技術も重要で、オンライン上でのファンコミュニティの構築や運営方法を学ぶことで、より深いエンゲージメントを生み出せます。これらの技術を組み合わせることで、単なる情報発信者から戦略的なデジタルマーケターへとステップアップできます。
広報でSNS担当を成功させるプラットフォーム別戦略
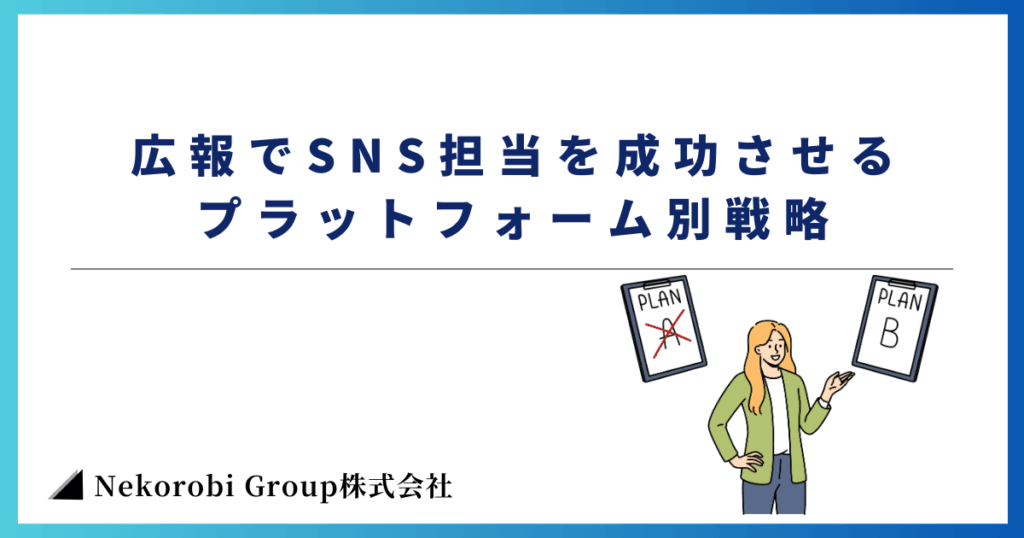
Twitter(X)での広報戦略
Twitter(現X)は即時性と拡散力が最大の特徴であり、広報のSNS担当者にとって重要なプラットフォームです。140文字という制限の中で企業メッセージを効果的に伝えるには、簡潔で印象的な表現力が求められます。リアルタイムでの情報発信が可能なため、新商品の発表、イベントの告知、緊急時の対応などに適しています。また、ハッシュタグを効果的に活用することで、ターゲット層への到達率を高めることができます。
Twitterでの成功の鍵は、トレンドへの敏感さと迅速な対応力です。話題になっているキーワードやイベントに関連付けた投稿を行うことで、通常よりも多くのユーザーにリーチできます。ただし、企業アカウントとしての品格を保ちながら、親しみやすさを演出するバランス感覚が重要です。また、他の企業アカウントや業界関係者との交流を通じて、ネットワークを構築することも効果的な戦略の一つです。リツイートやリプライを活用したコミュニケーションにより、企業の人間味を表現できます。
Instagram・YouTube・LINEでの広報戦略
Instagramは視覚的コンテンツが中心のプラットフォームであり、広報のSNS担当者にはクリエイティブな表現力が求められます。商品の魅力を写真や動画で伝える技術、ブランドの世界観を一貫して表現するデザインセンス、そしてストーリーズ機能を活用したリアルタイムな情報発信が重要です。フィード投稿では統一感のある世界観を構築し、ストーリーズではより親近感のある日常的な情報を発信することで、フォロワーとの距離を縮めることができます。
YouTubeでの広報活動は、詳細な商品説明や企業の取り組みを動画で紹介することが主目的となります。チュートリアル動画、社内の様子、代表者のメッセージなど、テキストや静止画では伝えきれない情報を効果的に発信できます。動画制作には時間とコストがかかりますが、一度制作したコンテンツは長期間にわたって視聴され続けるため、費用対効果の高い施策といえます。LINEでは、より密接な顧客関係の構築が可能で、クーポン配信や限定情報の提供を通じて顧客ロイヤリティを高めることができます。
BtoB企業向けSNS戦略
BtoB企業の広報でSNS担当者が活用すべきプラットフォームは、BtoC企業とは異なる特性があります。LinkedInは特にBtoB企業にとって重要で、業界の専門性を活かした情報発信や、他企業の担当者とのネットワーキングが可能です。技術的な解説記事、業界動向の分析、導入事例の紹介など、専門性の高いコンテンツが評価される傾向があります。また、企業の経営陣による思考リーダーシップの発信も効果的です。
Facebookも BtoB企業にとって有効なプラットフォームです。比較的年齢層の高いユーザーが多く、意思決定者層へのリーチが期待できます。企業ページでは詳細な商品情報や導入事例、ウェビナーの告知などを発信し、見込み客の獲得につなげることができます。BtoB企業のSNS戦略では、直接的な販売促進よりも、信頼関係の構築や専門性のアピールに重点を置くことが重要です。継続的な有益な情報発信により、業界内でのポジショニングを確立することが長期的な成功につながります。
広報のSNS担当で注意すべきリスクと対策
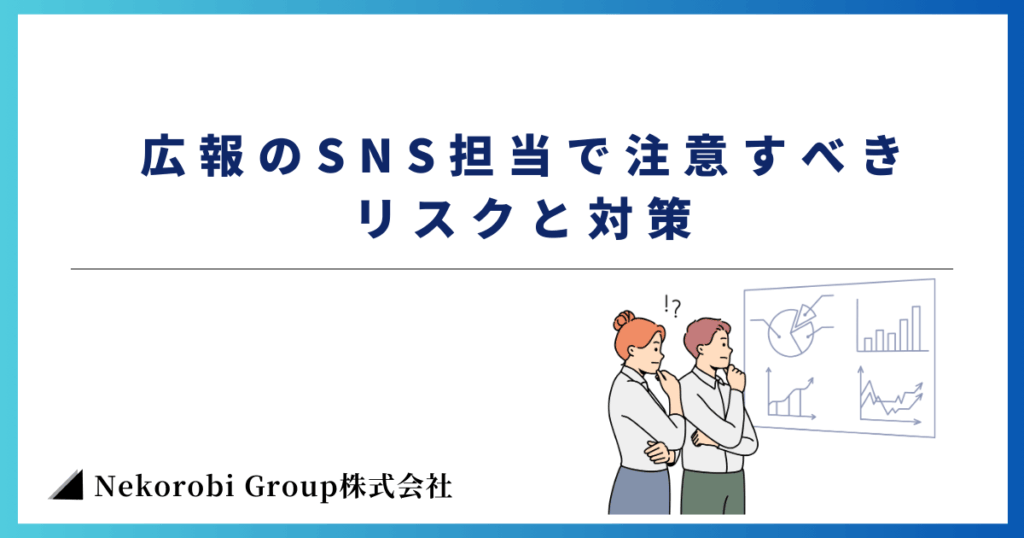
炎上リスクとその予防策
広報のSNS担当者が最も警戒すべきリスクは炎上です。一度の不適切な投稿が企業の信頼性を大きく損なう可能性があります。炎上の主な原因として、社会情勢に対する配慮不足、差別的な表現、競合他社への批判、個人的な意見の混入などが挙げられます。これらを防ぐためには、投稿前の複数人によるチェック体制が不可欠です。特に敏感な話題については、法務部門や上司への事前確認を徹底することが重要です。
炎上リスクを最小限に抑えるためには、平時からの準備が重要です。炎上が発生した場合の対応マニュアルを作成し、関係者間で共有しておくことで、迅速かつ適切な対応が可能になります。また、ソーシャルリスニングツールを活用して、自社に関する投稿やコメントを常時モニタリングし、問題の兆候を早期発見することも効果的です。万が一炎上が発生した場合は、感情的な反応を避け、事実確認を行った上で、必要に応じて謝罪や訂正を行います。透明性と誠実性を保った対応が、信頼回復への近道となります。
法的リスクへの対応
広報のSNS担当者は、情報発信に伴う法的リスクについても十分な理解が必要です。著作権侵害は最も身近なリスクの一つで、他社の画像や音楽の無断使用、引用範囲を超えた文章の転載などが問題となります。商用利用可能な素材の活用や、適切な引用方法の習得が重要です。また、肖像権についても注意が必要で、社員や顧客の写真を投稿する際は、事前に使用許可を得ることが基本です。
景品表示法との関係も重要な法的リスクです。過大な効果を謳った商品紹介や、根拠のない比較表現は法的問題に発展する可能性があります。薬機法(医薬品医療機器法)についても、健康食品や化粧品を扱う企業では特に注意が必要です。これらの法的リスクを回避するためには、定期的な法務研修の受講や、専門家への相談体制の構築が有効です。当社のような代行サービスでは、これらの法的リスクを熟知した専門スタッフが対応するため、安心してお任せいただけます。
ブランドイメージ保護のポイント
企業のブランドイメージを保護するためには、一貫性のあるメッセージ発信が重要です。広報のSNS担当者は、企業の価値観やミッションを深く理解し、それらを反映した投稿を継続的に行う必要があります。また、異なるプラットフォーム間でも統一されたトーンやビジュアルアイデンティティを維持することで、ブランドの認知度と信頼性を高めることができます。投稿の際は、その内容が企業のブランドイメージに与える影響を常に考慮することが重要です。
ステークホルダーとの関係維持も重要な要素です。顧客、取引先、従業員、株主など、様々な立場の人々がSNSを通じて企業の発信を見ています。特定のグループに偏った内容ではなく、すべてのステークホルダーに配慮したバランスの取れた情報発信を心がけることが必要です。また、危機管理の観点から、ネガティブな情報が拡散される前に適切な対応を行うことも重要です。定期的なブランドイメージの調査や分析を行い、必要に応じて戦略の見直しを行うことで、長期的なブランド価値の向上につなげることができます。
広報のSNS担当を社内で育成する方法
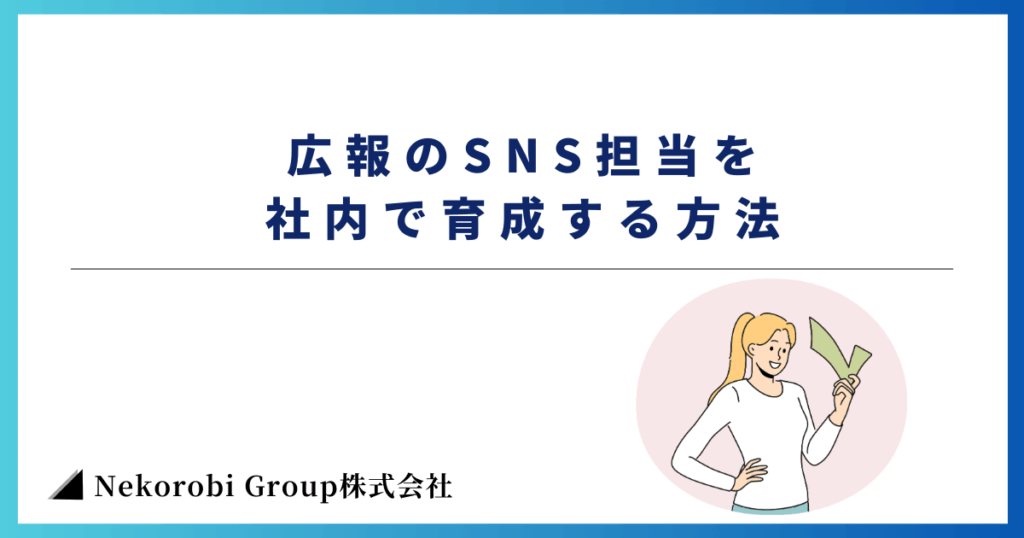
適任者の選び方
広報のSNS担当者として適任な人材を社内で選ぶ際は、まずコミュニケーション能力の高さを重視することが重要です。社内外の様々な人との円滑な関係構築ができ、文字でのやり取りでも相手の意図を正確に理解できる人材が理想的です。また、普段からSNSを個人的に利用しており、各プラットフォームの特性や機能を理解している人材を選ぶことで、学習コストを削減できます。ただし、個人での利用と企業アカウントの運用は大きく異なるため、プライベートと仕事の切り分けができる人材であることが前提条件となります。
企業理解の深さも重要な選考基準です。自社の商品・サービス、企業理念、業界知識を十分に理解している人材であれば、適切な情報発信が期待できます。また、責任感が強く、継続的な業務遂行が可能な人材を選ぶことも重要です。SNS運用は日々の積み重ねが成果につながるため、長期間にわたって安定した業務遂行ができる人材が適しています。さらに、新しい技術やトレンドに対する学習意欲があり、変化に柔軟に対応できる人材であることも重要な要素です。
効果的な研修・教育プログラム
広報のSNS担当者を社内で育成するためには、体系的な研修プログラムが必要です。まず、SNSマーケティングの基礎知識から始め、各プラットフォームの特性、ターゲット層の分析方法、コンテンツ制作の基本などを学習します。座学だけでなく、実際に投稿を作成し、上司や先輩からフィードバックを受ける実践的な研修も重要です。また、競合他社の成功事例や失敗事例を分析することで、効果的な運用方法と避けるべきリスクを学習できます。
継続的なスキルアップ支援も重要な要素です。外部セミナーへの参加、業界専門書の購読費用補助、資格取得支援などを通じて、常に最新の知識やスキルを習得できる環境を整備します。また、定期的な振り返りミーティングを実施し、業務の課題や改善点を共有することで、継続的な成長を促進できます。メンター制度の導入により、経験豊富な先輩からの指導を受けられる体制を構築することも効果的です。これらの取り組みにより、社内でのSNS担当者の育成が可能になります。
組織体制の整備
効果的なSNS運用のためには、適切な組織体制の整備が不可欠です。SNS担当者の責任範囲を明確に定義し、他部署との連携体制を構築することが重要です。商品企画部門からの新商品情報、営業部門からの顧客の声、人事部門からの採用情報など、様々な部署からの情報を効率的に収集し、SNSでの発信に活用する仕組みを作ります。また、法務チェックやブランド管理部門との連携により、リスク管理体制も整備します。
承認フローの最適化も重要な要素です。迅速な情報発信とリスク管理のバランスを取るため、通常の投稿と緊急時の投稿で異なる承認フローを設定します。また、SNS担当者が一人の場合のバックアップ体制も重要で、休暇時や緊急時に代替対応ができる人材を確保しておくことが必要です。定期的な組織体制の見直しを行い、業務量の増加や新しいプラットフォームへの対応に合わせて体制を調整することで、継続的な改善を図ることができます。
広報のSNS担当を外部委託する選択肢
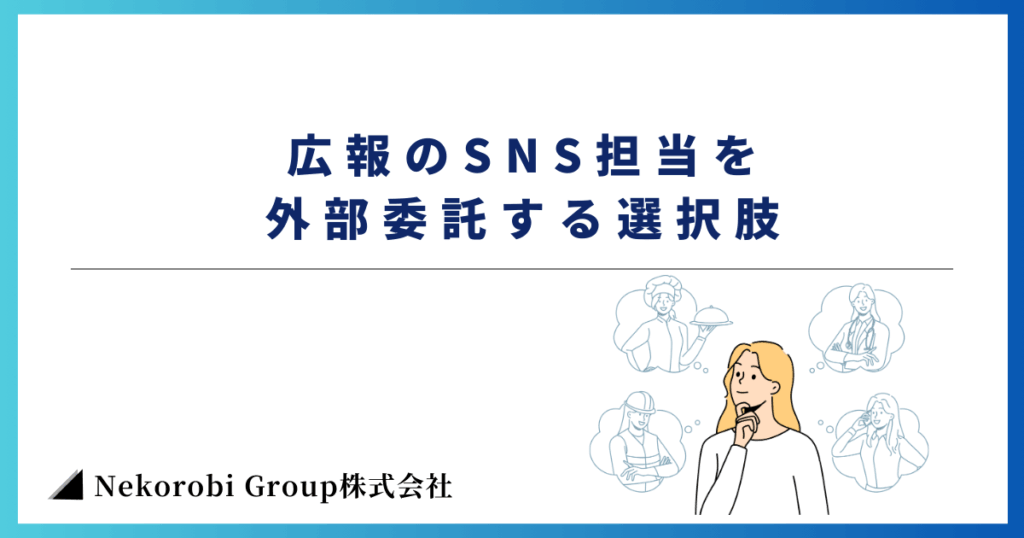
外部委託のメリット・デメリット
広報のSNS担当業務を外部委託することには、多くのメリットがあります。最大の利点は、専門的な知識と経験を持つプロフェッショナルに業務を任せられることです。当社のような代行サービスでは、様々な業界での豊富な経験を持つスタッフが、最新のトレンドや効果的な手法を活用してSNS運用を行います。また、複数の専門スタッフがチームとして対応するため、一人の担当者に依存するリスクを回避できます。さらに、即座に業務を開始できるため、社内での人材育成にかかる時間とコストを削減できます。
一方で、外部委託にはデメリットも存在します。社内の詳細な商品知識や企業文化を理解するまでに時間がかかる場合があります。また、委託費用が継続的に発生するため、長期的なコスト面での検討が必要です。さらに、社内にノウハウが蓄積されにくいという課題もあります。ただし、当社では定期的な報告会や戦略会議を通じて、クライアント企業との密接な連携を図り、これらの課題を最小限に抑える努力をしています。また、業務の一部を段階的に内製化するサポートも提供しており、将来的な自社運用への移行も可能です。
委託先選びのポイント
広報のSNS担当業務を外部委託する際の委託先選びでは、まず実績と経験を重視することが重要です。同業界や類似規模の企業での成功事例があるかを確認し、具体的な成果データを提示してもらうことで、サービスの質を判断できます。また、チーム体制や担当者のスキルレベルも重要な選定基準です。単なる投稿代行ではなく、戦略立案から効果測定まで一貫して対応できる体制があるかを確認することが必要です。
コミュニケーション体制も重要な要素です。定期的な報告頻度、緊急時の連絡体制、戦略変更時の対応フローなどを事前に確認しておくことで、円滑な委託関係を構築できます。当社では、専用の担当者を配置し、月次の詳細レポートと週次の進捗報告を行うことで、透明性の高いサービス提供を心がけています。また、業界の法的規制や炎上リスクへの対応力も重要な選定基準です。過去のトラブル事例への対応実績や、リスク管理体制について詳しく説明を求めることをお勧めします。
内製と外注の使い分け戦略
効果的なSNS運用のためには、すべてを内製化する必要はありません。業務の特性に応じて内製と外注を使い分けることで、コストパフォーマンスを最大化できます。例えば、商品の詳細説明や技術的な内容は社内の専門スタッフが対応し、コンテンツの制作や投稿スケジュール管理は外部委託するという方法が効果的です。また、立ち上げ期は外部委託で基盤を構築し、運用が軌道に乗った段階で段階的に内製化を進めるアプローチも有効です。
当社では、クライアントの成長段階に合わせた柔軟なサービス提供を行っています。初期段階では完全代行サービスで迅速な立ち上げを支援し、その後は社内スタッフとの協働モデルへ移行、最終的には自社での運用が可能になるまでサポートを継続します。この段階的なアプローチにより、外部委託のメリットを享受しながら、社内にもノウハウを蓄積することができます。また、特定のプラットフォームのみを委託し、他は内製で行うという部分委託も可能で、企業の状況に応じて最適な運用体制を構築できます。
まとめ
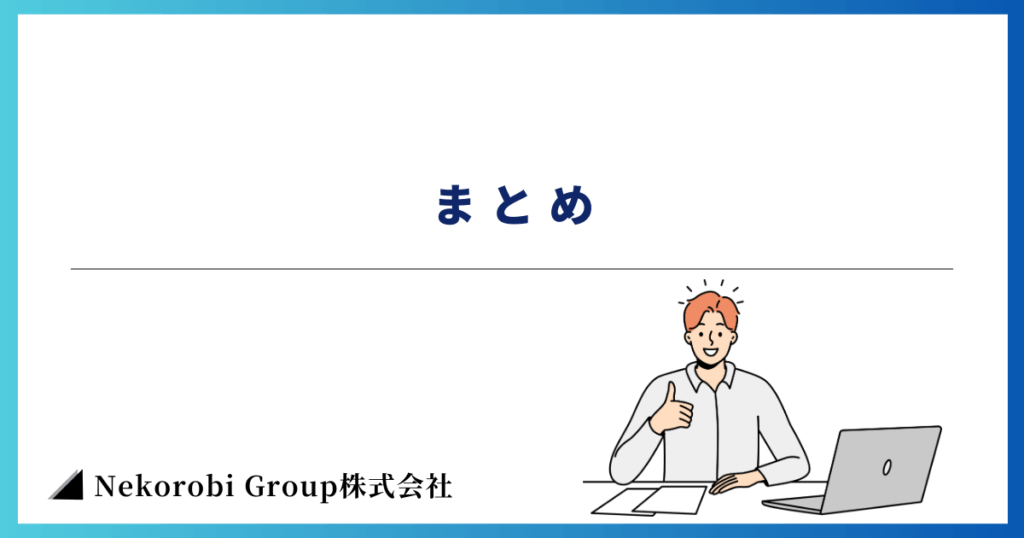
広報におけるSNS担当者は、現代企業にとって欠かせない存在となっています。単なる投稿作業者ではなく、企業のブランディング戦略の最前線で活躍する専門職として、多岐にわたる業務を担当します。戦略立案から日々のコンテンツ制作、ユーザーとのコミュニケーション、効果測定まで、その責任範囲は広範囲にわたります。
成功するSNS担当者には、優れたコミュニケーション能力、データ分析力、継続力、そして常に学習し続ける姿勢が求められます。また、各SNSプラットフォームの特性を理解し、ターゲット層に応じた適切な情報発信を行う技術も必要です。一方で、炎上リスクや法的リスクなど、注意すべき点も多く、専門的な知識と経験が不可欠です。
社内でSNS担当者を育成することも可能ですが、適切な人材の選定、体系的な研修プログラム、組織体制の整備など、多くの準備が必要です。特に中小企業においては、限られたリソースの中で効果的なSNS運用を実現するために、外部の専門サービスを活用することも有効な選択肢です。
当社のような代行サービスでは、豊富な経験と専門知識を持つスタッフが、クライアントの業界特性や企業文化を理解した上で、最適なSNS戦略を提案・実行いたします。また、内製化への移行サポートも含めた包括的なサービスを提供しており、企業の成長段階に応じた柔軟な対応が可能です。
SNS運用は継続的な取り組みが成果につながる分野です。自社での対応にご不安がある場合や、より効果的な運用をお求めの場合は、お気軽にお問い合わせください。専門チームが貴社の状況に応じた最適なソリューションをご提案いたします。
文字数:約7,850文字